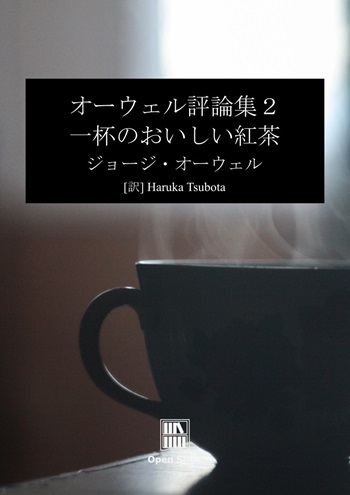一書評家の告白
寒く、しかし空気のよどんだワンルーム・アパート、タバコの吸い殻と飲みかけの紅茶のカップが雑然と置かれたそこで虫に食われた部屋着を着た一人の男がおんぼろのテーブルに向かい、周りに積まれた埃っぽい書類をどかしてタイプライターを置く場所を作ろうとしている。紙の束を捨てることはできない。ごみ箱はすでにあふれかえっているし、返事を書いてない手紙や払っていない請求書の束のどこかに二ギニーの小切手があるかもしれないのだ。それを銀行へ払い込むのを忘れていることはまず間違いなかった。住所録に書き留めておく必要のある住所が書かれた手紙だってある。住所録はどこかに失くしてしまっていて、それを、あるいは他の何かだったかもしれないが、探そうという考えがひどい自暴自棄の衝動とともに彼を悩ませていた。
彼の歳は三十五だったが、見かけは五十だった。禿げ上がり、静脈瘤持ちで眼鏡をかけていたが、それもいつもどこかにいってしまうたったひとつの眼鏡が手元にある時だけだ。普段は栄養失調に苦しんでいるが、幸運が続いているときには二日酔いで苦しんでいる。今は午前十一時を三十分過ぎたところで、予定では二時間前には仕事に取りかかっていなければならなかった。しかしたとえもし真剣に取りかかろうと努力したところで、ほとんどひと時も絶えずに鳴り続ける電話のベルや赤ん坊の喚き声、通りから聞こえてくる電動ドリルの騒音、借金取りの重いブーツが階段を上り下りする音に苛立たされることだろう。直近にはいった邪魔は二度目の郵便屋の来訪で、それは二通のチラシと赤字で印刷された税金の督促状を届けに来たものだった。
この人物が文筆業の人間であることは言うまでもない。おそらく詩人か小説家、あるいは映画脚本かラジオの特集を書く作家か。文筆を生業にする人間は皆、とてもよく似ている。しかしここでは書評家であることにしておこう。積まれた書類に半ば埋もれているのは編集者から送られてきた五冊の本が入った分厚い小包で、そこにはこれらは「合わせて読むべきである」と書かれたメモが添えられている。それが届いたのは四日前だが、倫理観の欠如からその書評家は四十八時間の間、小包を開かずにいた。昨日、決意が固まった瞬間を見計らって彼は小包のひもを解き、その五冊が岐路に立つパレスチナ、科学的酪農、ヨーロッパ民主主義小史(これは六八〇ページで、四ポンドの重さがあった)、ポルトガル領東アフリカの習俗、そして心地よい横たえという小説であることを見て取った。最後のものはおそらく手違いで加えられたものだろう。書評……八百ワードと言われていた……は明日の正午が締め切りだった。
本のうちの三冊は彼がまったく知らないテーマを扱っていて、著者(彼らはもちろん書評家の習性をよく知っている)だけでなく一般読者の信頼を失うような馬鹿な間違いをしでかしたくなければ少なくとも五十ページは読まなければならない。午後四時には包み紙から本を取り出しているだろうが、いまだそれを開くだけの気力がわかないことに彼は苦しんでいるはずだ。それを読むことを思うと、さらにはその紙の匂いをかぐだけでひまし油風味の冷えた米粉プディングを食べているような気持ちになる。それにも関わらず奇妙なことに彼の原稿は締め切りまでに編集部に届くのだ。どうしたわけかいつだって原稿は間に合う。午後九時ごろになると彼の頭は比較的さえてくる。だんだん冷えてくる部屋に深夜になるまで座りこみ、どんどん濃くなっていくタバコの煙の中で本を次から次に巧みに飛ばし読みしては最後に論評の言葉とともに片付けていく。「まったく、なんて駄作だ!」。朝には目はかすみ、死んだような表情で、無精ひげは伸び放題だ。一、二時間、真っ白な原稿をじっとにらみ、それから威嚇する時計の針に脅されるようにして彼は作業にとりかかる。すると唐突に彼は集中した状態になるのだ。使い古されたフレーズ……「誰しもが読むべき一冊」、「全てのページに記憶に残る何かがある」、「ひときわ価値があるのはこれこれを扱っている章だ」……が、まるで鉄粉が磁石に吸い付けられるようにそれぞれの場所に飛んでいき、まさに必要なだけの長さの書評が残り時間の約三分前に書きあがる。そしてその一方で互いにちぐはぐで、食指の伸びない本の束が郵便で届けられるのだ。それが繰り返されていく。しかし、この虐げられ神経症気味の生き物が高い志とともにこの仕事を始めたのはほんの数年前のことなのだ。
おおげさ過ぎるだろうか? 私はあらゆる常連書評家……皆、年間に少なくとも百冊は書評している……に、その生活習慣と人物像は私が描写したようなものではないと心から否定できるかと尋ねたい。ともかく文筆業の人間は皆、多かれ少なかれこうした種類の人物なのだが長期にわたる見境のない書評はとりわけ報われず神経に障り疲弊する仕事だ。ごみくずを褒め上げるだけでなく……少し後で説明するように、それは避けられないにしても……何の感想もわかない本に向けて絶えず反応をでっちあげなければならない。書評家は……たとえそれにうんざりしていようとも……本に対して職業的な関心を抱き、年に数千冊も現れる中のおおよそ五十冊から百冊について執筆を楽しむ。一流の仕事をする者であれば、その中の十から二十をものにするだろうが、だいたいの場合、ものになるのは二つか三つだ。誠実に作品を褒めていようが貶していようが、残りの仕事は本質的にはいんちきもいいところなのだ。書評家は一度に半パイントずつ自らの不滅の魂を下水管に注ぎ込んでいるのだ。
書評家の大多数は扱っている本について不十分か、誤解を招くような説明をおこなう。戦争戦争:第二次世界大戦を指す以来、出版社が文芸編集者に口出ししたり、生み出された本の全てに称賛の声をあげさせたりすることは以前よりも難しくなっているが、一方で紙面の欠乏やその他の不都合によって書評の水準は低下している。結果を見るに、物書きの手から書評を取り上げることこそが解決策であると人々は考えているようだ。特殊なテーマを扱った本は専門家が扱うべきだが、一方でかなりの量の書評、とりわけ小説のそれはアマチュアによっておこなわれている。それが激しい嫌悪の感情であるにせよ、たいていの本は激しい感情を喚起させることができる。読者のなかにはそれへの自分たちの感想こそが専門家による退屈な感想よりも価値のあるものなのだと考える者もいるだろう。しかし残念ながら、編集者であれば誰もが知るようにこうした種類のものは組織化することが非常に難しい。実際のところ、編集者とは常に自らの物書きの一団……彼らが呼ぶところの「常備軍」……へと戻っていくものなのだ。
全ての本は評論に値するのだと考える限り、これは仕方のないことだ。大量の本について語る時にはその大多数に対して過大な評価を与えずに済ますことさえほとんど不可能なのだ。本を扱う仕事に就いて初めて人はその大多数がどれほど粗悪なものであるかに気がつく。客観的で誠実な批判をおこなえば九割を超えるものに対して与えられる評価は「この本は無価値だ」というものだし、実際のところ書評家がそれらにとる反応は「この本にはまったく興味がわかない。金を貰わなければこれについて何か書こうとは思わない」というものだろう。しかし一般の人々はそういったものを読むために金を払おうとはしないだろう。なぜそんな必要が? 彼らが欲しいのは読むように言われた本の案内書きのようなもの、鑑定書のようなものなのだ。だが価値について語るときには物差しは役には立たない。例えば……ほとんどの書評家が週に一度はこういった種類のことを言うが……リア王は優れた戯曲であるだとか、正義の四人は優れたスリラー小説だと言うとき、この「優れた」という言葉はいったい何を意味するのだろうか?
私は常に思うのだが、もっとも良い方法はたんに大多数の本を無視し、取り上げるに値するように思われる少数のものに非常に長い書評……最低でも千ワード……を与えることなのではないだろうか。近刊書に対する一、二行の短いメモ書きであれば役にも立つだろうが、六百ワードほどの中くらいの長さの書評はたとえもし書評家が本心からそれを書きたいと思ったものであっても無価値なものにならざるを得ない。通常、書評家はそういったものを書きたがらないし、毎週毎週そういった断片を生み出していると書評家はこの記事の冒頭で私が描写したような、部屋着を身にまとったくたびれた姿に成り下がるのだ。しかし下には下がいる。どちらの仕事もおこなった経験からすると書評家は映画評論家よりはましだと言わざるを得ない。映画評論家は自宅で仕事をすることすらできないのに、午前十一時の見本市には参加しなければならず、数人の著名な例外を別にすれば、一杯の安いシェリー酒と引き換えに自らの誠実さを売り渡すことを期待されているのだ。