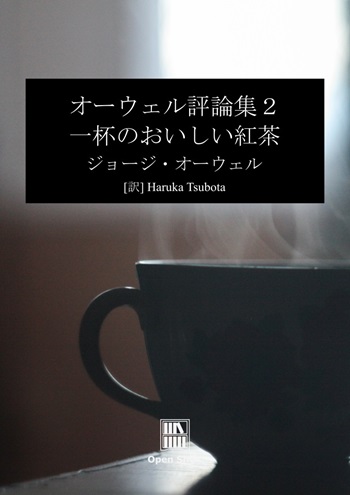貧しい者の死に様
一九二九年のことだ。私はパリの第十五区のとある病院で数週間を過ごした。そこの受付係は受付で私をお決まりの厳しい尋問にかけ、中に入れてもらえるまで二十分ほどにわたって私は質問に答え続けた。もしラテン系の国で問診票を埋めるはめになったことがあれば、質問がどのようなものだったかはわかるだろう。私は過去数日に渡って誤って列氏温度を華氏温度と取り違えていたのだが、自分の熱が一〇三度自分の熱が一〇三度:摂氏温度だと約39.4度ほどであることはわかっていて問診が終わるころには自分の足で立つのも難しくなっていた。背後には諦めきったような患者の一団がいた。カラフルなハンカチの包みを下げ、自分の問診の順番が来るのを待っているのだ。
問診が終わると風呂だ……刑務所や救貧院と同じようにこれは新参者全員に課せられた決まり事だ。衣服をはぎ取られて震えながら五インチほどのぬるい湯の中に何分か座った後でリネンの寝間着と丈の短い青いフランネルの部屋着を与えられ……どれも私には小さすぎると言われてスリッパは無かった……外へと連れていかれた。二月の夜のことで、私は肺炎で苦しんでいるところだ。向かう先の病室は二百ヤード向こうにあって、たどり着くには病院の敷地を横切らなければならないようだった。ランタンを持った誰かが私の前でよろめく。砂利の敷かれた道は足元で凍りつき、風が私の素足のふくらはぎの周りで寝間着をはためかせた。病室へ足を踏み入れた時、私は奇妙な懐かしさを感じた。それが何に由来するものなのか夜遅くになるまで私は気が付けなかった。長細く、妙に天井の低い薄暗い部屋だった。うめく声が満ち、三列に並べられたベッドは驚くほど互いに近かった。糞便と何か甘ったるいもの混ざった息の詰まるような臭いがした。倒れこみながら見ると私の反対側の近くに小柄で猫背の薄茶色の髪をした男が半裸になって座っていて、医者と学生が彼に何か奇妙なことをしていた。まず医者が自分の黒鞄から一ダースほどのワイングラスのようなガラス製のグラスを取り出し、次に学生がマッチを燃やしてそれぞれのグラスから空気を抜いた。そして急いでそのグラスを男の背中や胸に乗せると、男の体が吸引されて大きな黄色い水ぶくれのようになるのだ。しばらくして彼らが男に何をしているのかに私は気がついた。それは吸角法と呼ばれるものだった。古い医学書には載っている治療法だが、その瞬間まで私は漠然とそれは馬に施すものだと思っていた。
おそらく冷たい外気が私の熱を冷ましたのだろう。私はこの野蛮な治療を平然と、いやむしろいくぶん楽しむように観察した。しかし次の瞬間、医者と学生は私のベッドへとやって来て無言で私の体を引き起こすと同じグラスで治療を始めた。まったく消毒していないグラスだ。私の弱々しい抗議の訴えは何の反応も引き起こさず、自分が動物になったかのようだった。この二人が私を見る目つきの非人間的な様子は私に深く印象を残した。病院の大部屋に入ったことはそれまで一度もなかった。医者が無言のまま、人間的な意味での声をかけることもなく処置するのを体験したのは初めての経験だったのだ。私の場合には使われたグラスは六つだけだったが、いったん処置が終わると水ぶくれから引きはがして再びグラスを張り付けられた。今度はそれぞれのグラスにデザートスプーン一杯ほどの黒っぽい血が吸い出された。自分におこなわれた行為に対する屈辱と吐き気と恐怖で再び倒れこみながら、少なくともあとは放っておいてくれるだろうと私は考えた。しかしそれは大きな間違いだった。次の治療、マスタードの湿布が始まった。見たところあの温水浴と同様、これはお決まりの処置らしかった。二人のぞんざいな態度の看護師がすでに湿布を準備していて、私の胸にそれを拘束衣のようにきつく巻きつけた。その間にシャツとズボン姿で病室を歩き回っていた何人かの男たちが半ば同情するような笑みを浮かべて私のベッドの周りに群がってきた。後になって知ったことだがマスタードの湿布をされた患者を見物するのはその病室での人気の娯楽のひとつだったのだ。この処置は普通は十五分ほど続き、自分が関係者にならない場合には確かにおもしろおかしいものだ。最初の五分間の痛みはひどいものだが、まだ耐えられそうに思う。次の五分間でこの考えは消え去るが、湿布は背中の側で留められているので剥がすことができない。見物人が一番楽しむのがこの時間だ。最後の五分間では気がつくと一種の無感覚状態に陥っている。湿布が取り除かれると氷が詰められた水枕が頭の下に押し込まれ、私は放置された。私は眠らなかった。記憶にある限りではこれは人生で唯一のことだ……つまりベッドの中に入って一分たりとも眠らずに過ごしたのはこの夜だけなのだ。
とある病院での最初の一時間で私は一連のさまざまな、互いに矛盾した治療を受けたがこれは誤解を生みだすものだった。全般的に見て受けられる治療はそれが良いものであれ、悪いものであれ非常に少なかった。例外があるとすればそれは興味深い、教育的に有用な病気にかかっている場合だけだ。朝五時になると看護師が巡回して患者を起こしては体温を計るが、洗濯はしてくれない。十分に体調が戻っていれば自分でするし、そうでなければ歩ける患者の思いやりにすがるしかない。尿瓶やラ・キャセロールというあだ名が付けられている金属製の不快な携帯便器を運ぶのも基本的には患者だ。八時になると朝食が運ばれてくる。軍隊風ラ・スープと呼ばれるものだ。これまた水っぽい野菜スープで、中にけち臭いぶよぶよしたパンが浮いている。昼も遅くなると背の高い真面目くさった顔の、黒いひげを生やした医者が回診を始め、彼の後ろを一人のインターンと、学生の一群が付いて回る。その病室には私たち六十人ほどがいたが、彼が他にも病室を抱えていることは明らかだった。気管支喘鳴の非常にいい見本だった私自身も、胸の聴診をしようと列になった一ダースほどの学生の相手をときどきした。非常に奇妙な感覚だった……なぜ奇妙だったかと言えば、技術を学ぼうという彼らの熱心な関心と同時に、患者は人間であるという感覚の欠如がうかがえたからだ。奇妙と言えば、自分の番が回って来た若い学生の何人かが興奮で文字通り震えだしそうだったこともあった。まるで高価な機械の部品をついに手に入れた少年のようだったのだ。そして次から次に耳が背中に押し付けられる……若い男の耳、若い女の耳、黒人の耳……そして次は厳かに、しかし不器用に触診だ。そして彼らの誰一人として一言の会話もしようとはせず、直に顔を見ようともしないのだ。決められた寝間着を着た治療費を払えない患者は基本的には標本なのだ。不快は感じなかったが決して慣れることはできなかった。
何日か経つと私は体を起こして周りの患者を観察できるまでに回復した。息の詰まるような室内には狭いベッドが隣の者に簡単に触れられるほど所狭しと並べられ、あらゆる種類の病気が見て取れた。感染力の強い伝染病以外はすべて存在したのではないかと思う。右手側の隣人氏は小柄な赤毛の靴屋で、片足がもう一方の足より短かった。彼はよく口笛を吹いて他の患者の死(これは何度も起きたが最初に気が付くのは決まって私の隣人なのだ)を私に知らせた。「四十三番だ!」(あるいは他の番号)と叫ぶと頭の上に両腕を振り上げる。この男はそう具合が悪そうでもなかったが、私の視界に入る他のベッドのほとんどではみじめな悲劇やひどく恐ろしいことが起きていた。私のベッドと足を突き合わせるように置かれたベッドには、死にゆく(死ぬ瞬間は見ていない……彼は他のベッドに移されたのだ)小柄なひからびた男が横たわっていた。彼が何の病気で苦しんでいるのか私にはわからなかったが、全身がひどく過敏になっていてあらゆる動作、時には毛布の重みにさえ彼は痛みの叫びをあげた。排尿をする時が一番苦しいらしく、ひどく難儀していた。看護師が彼のベッドに尿瓶を持ってくる。それから長いことベッドのわきに立って馬丁が馬にやってやるようにシー、シーと声をかけると、ようやく「Je fissel」という苦痛の金切り声とともに彼が催すのだ。彼の隣のベッドには薄茶色の髪の男がいて、四六時中、咳をしては血の混じった粘液を器に吐いていた。私の左手側の隣人は背の高い、弛緩したような見かけの若い男で、定期的に背中に管を差し込まれ、驚くほどの量の泡立った液体を体のどこからか抜かれていた。その向こうのベッドでは一八七〇年の戦争一八七〇年の戦争:普仏戦争を指すの退役兵が死にかかっていた。白い皇帝ひげを生やした、顔立ちの整った老人で、面会時間中は常にベッドの周りを四人の黒衣の年配女性の親戚が囲んで座っていた。まるでカラスのようだったが、わずかばかりの遺産を狙ってのことなのは明らかだった。私の反対側、遠い方のベッドには年取った禿げ頭の男がいた。口ひげを垂らし、顔と体は腫れ上がり、何か絶えず尿意を催させる病気に苦しんでいた。ベッドのわきにはいつも巨大なガラス製の容器が置かれていた。ある日、彼の妻と娘が面会に訪れた。二人を目にすると老人の膨れ上がった顔が驚きと喜びの笑顔に包まれた。娘は二十歳ほどの魅力的な女性だったが、彼女がベッドに近づくと彼の手が毛布の下からゆっくりと出されるのが見えた。その動きに私は、彼女がベッドのわきにひざまずき老人が彼女の頭に手を置いて最後の祈りをするのかと思った。しかし違った。彼はただ尿瓶を彼女に手渡し、彼女はそれをすばやく受け取ると先ほどの容器にあけて空にしたのだった。
私のところからベッド一ダースほど離れたところに五十七番……それが彼の番号だったと思う……がいた。肝硬変の患者だ。病室の誰もがその顔を知っていた。ときどき彼が医学講義の題材になっていたからだ。週に二度、午後になるとあの背の高い真面目くさった顔の医者が病室の真ん中で学生の集団に講義をおこなうのだ。年老いた五十七番は一度ならず台車のようなもので病室の中央に運び出されていた。そこで医者は彼の部屋着を捲りあげ、腹の上の大きなたるんだ突起……病変した肝臓なのではないかと思うが……を指で広げながら、これはアルコール依存症による病気でワインを飲む国では一般的なものであると生真面目に説明した。常のごとく患者に向けては話しかけないし、笑いかけたり、頷いたりといった相手に気を配るしぐさも見せない。真面目な調子で背を伸ばして話す間、医者は両腕を衰えた男の体の上に置いて、ときどき穏やかに体の向きを変えさせた。その様子はまるで女性が綿棒で小麦をこねているかのようだった。五十七番がこういったことを嫌がっているというわけではなかった。見るからに彼は古参の入院患者で、講義の題材の常連だった。その肝臓はずっと前から病理学博物館のホルマリン標本用にと目をつけられているのだ。自分について言われていることに全くの無関心なまま、彼は生気の無い目で中空を見つめて横たわり、医者はまるでアンティークの磁器のひとつのように彼を披露していった。六十歳ほどの驚くほど体が萎縮した男だった。顔は羊皮紙のように青ざめ、人形と変わらないのではないかと思うほど小さく縮んでいた。
ある朝、靴屋の隣人が枕を引っ張って私を起こした。看護師が現れる前のことだ。「五十七番だ!」……彼は両腕を頭上に振り上げた。病室は明るく、それを目にするのには十分だった。年老いた五十七番が、脇を下にねじれるような恰好で横たわっているのが見えた。ベッドの横に突き出された顔は私の方を向いていた。何時かわからないが夜のうちに彼は死に、誰もその時にはそれに気がつかなかったのだ。やって来た看護師は、彼の死の知らせを無表情で聞くと自分の仕事に戻っていった。一時間以上だろうか、長い時間がたった後、二人の別の看護師が木靴の大きな音を立てながらまるで兵士のように並んで歩いてくると、死体をシーツで包んだが死体はその後も運び出されるまでしばらくそのままにされた。その間にも部屋はさらに明るくなって五十七番をよく見ることができた。彼が見える向きに私は体を横たえていたのだ。なんともおかしな話だが、彼は私が目にした初めての死んだヨーロッパ系の人間だったのだ。以前にも死人を目にしたことはあったがそれは決まってアジア系で、だいたいは暴力によって死んだ人々だった。五十七番の目はまだ開かれたままで口もそうだった。その小さな顔は苦痛の表情に歪んでいた。しかし最も私に印象を残したのはその顔の白さだった。以前は青白かったが、今では体を覆うシーツより少し薄黒い程度だ。その小さな歪んだ顔を見つめるうちに、台車で運び去られ解剖室の遺体安置台の上に放り出されるのを待つこの胸の悪くなるような遺棄物が「自然」死のひとつの例であるという事実、礼拝での祈りで願われるもののひとつであるという事実が私を襲った。そう、そうなのだ。私は思った。これこそ二十年、三十年、四十年後に待ち受けているものなのだ。高齢になるまで生き延びた幸運な者の死に様なのだ。もちろん人は生きようと望む。死への恐怖によって生に留まるのだ。しかしその時考えたように、今では私はあまり歳をとらずに暴力によって死ぬ方が良いと考えている。人々は戦争の恐ろしさを語る。しかし一般的な病のどれかにでも残酷さで匹敵するような兵器が人間によって発明されたことがあるだろうか? 「自然」死は、その定義からしても、なにかゆっくりと進む、悪臭を放ち、痛みに満ちたものを意味するのだ。たとえそうだとしても公共の施設ではなく自らの家でそれに到達するのであれば違いもあろう。ろうそくの燃えさしのように消え消えになったこの貧しく、年老いた気の毒な男は、誰にも看取られないほど無価値だったのだ。彼はたんなる番号であり、学生のメスの「題材」だった。そしてこんな場所で死に様をみじめにさらしているのだ! きっと「小便が漏れちまう!」が彼の最後に残された言葉だったのではないかと思う。死を目前に控えた人間はそんなことを気にしたりはしないだろう……少なくともそれが普通の答えだ。しかし死を目前にした人々はその一日前、あるいはその瞬間まで、その頭の中はたいして普段と変わらないことが多いのだ。
病院の大部屋では、ここに自宅で死ねるような人間はいないのではないかという恐怖を感じる。ある種の病気はまるで貧しい人々を狙い撃ちしているかのようなのだ。しかし実際のところイギリスの病院であれば私があの病院で見たようなものを目にすることはないだろう。この困難に見舞われた人々はまるで動物のように死んでいく。そう、誰にも看取られず、誰にも構われず、その死は朝が来るまで気がつかれることさえない……これは一度ならず起きた。イギリスであればまず間違いなくこうしたことを目にする機会はないし、他の患者の視界に入る場所に遺体が置き去りにされるということもまずないだろう。昔、イギリスの小さな病院でお茶を飲んでいる最中に一人の男が死んだことがあった。病室には私たち六人しかいなかったが看護師が手早く処置をおこなったのでその男が死んだことにも、その体が運び出されたことにも、私たちはお茶が終わるまで気がつきもしなかった。イギリスで私たちが見落としがちなのは、よく訓練を積み、確固とした規律を持つ多くの看護師いるという恩恵に私たちが浴しているということだ。たしかにイギリスの看護師は愚かだ。お茶の葉で運を占い、イギリス国旗のバッジを着け、マントルピースには女王の写真を飾っていることだろう。しかし少なくとも不潔なままトイレにもいけないあなたをまったくの怠惰からむさ苦しいベッドに放置したりはしない。あのとある病院の看護師はいまだギャンプ夫人ギャンプ夫人:チャールズ・ディケンズの小説「マーティン・チャズルウィット」に登場する看護師の雰囲気を帯びていたし、後に共和スペインの軍病院で私が目にした看護師は体温を計ることもままならないほど無知だった。その後、自分で風呂にはいれるほど良くなった時、そこに病室から出た残飯と汚れた服が投げ込まれた大きな荷箱が置かれているのを私は見つけた。その羽目板には虫が群がっていた。自分の衣服を取り戻して自分の足で歩けるだけの力が戻ると、退院を待たず入院期間が終わる前に私はその病院から逃げ出した。病院から逃げ出したことは他にもあるがその陰鬱と露骨さ、息の詰まるような臭い、とりわけその雰囲気は私の記憶の中に際立って残っている。その病院を選んだのはそれが私の住んでいた街区にあったからで、中に入るまでそこが悪名高い場所だとは知らなかった。一、二年後、あの有名な詐欺師、マダム・アノーが拘留中に病気になってあの病院に入れられたという話を聞いた。数日後、彼女はなんとか看守の目を逃れるとタクシーを拾って拘置所まで戻って来た。そちらの方がまだ居心地がいいというのだ。当時でもあの病院がフランスの病院の典型から大きく外れていたであろうことは疑いない。しかしほぼすべて労働者だったあの患者たちは驚くほど諦観していた。彼らの何人かはあの状況を快適とさえ思っているようだった。そのうちの少なくとも二人は仮病の貧窮者で、彼らは冬を越すいい方法を見つけたと考えていた。仮病の人間は雑用をやらせるのに便利なので看護師は黙認していた。しかし大半の者の態度はこうだった。確かにここにはうんざりする、しかし他にどこに行けと? 朝五時に起きてから水っぽいスープで一日を始めるまで三時間待たされることも、誰にも看取られずに人々が死んでいかなければならないことも、治療を受けられるかどうかは医者が通りかかったときにその目に留まるかどうか次第ということさえも彼らの目には奇妙なこととは映らないのだ。彼らの伝統から言えば病院とはそういう場所なのだ。もし重い病気にかかり、自宅で治療を受けられないほど貧しければ病院に行くほかない。そしてそこに入ったら厳しい扱いと居心地の悪さに耐えなければならない。ちょうど軍隊に入隊するようなものだ。しかしとりわけ私の関心を引いたのは今ではイギリスではほとんど忘れ去られたような古い話に対する妄信を目にした時だ……例えば医者は純粋な好奇心から患者を切り刻むだとか、患者がちゃんと「理解」する前に手術を始めておもしろがるだとかいった話だ。浴室のすぐ上にあるという小さな手術室にまつわる怪談があった。その部屋から恐ろしい叫び声が聞こえるというのだ。そういった話の確証を得たことはないし、どれも馬鹿げた話であることは間違いない。しかし金を払っている患者にはおそらくしないであろう悪質な実験で二人の学生が十六歳の少年を殺した、あるいは殺しかけた(私が病院を去る時に彼は死にかけているように見えたが、おそらくはその後で回復したのだろう)のを私は確かに目にした。ある大きな病院で患者が解剖されて殺されたという話がロンドンで信じられていたことはまだ記憶に新しいところだ。あの病院ではその話が語られるのを聞いたことは無いが、耳にすればあそこの人間の一部はそれを信じるであろうことは間違いない。それはそこが病院だからということではなく、おそらくはかろうじて生きながらえている十九世紀の雰囲気のような何か、そしてそこに存在する特有の影響によるものだ。
過去五十年ほどの間に医者と患者の関係には大きな変化が起こってきた。十九世紀後半以前の文学作品を読めば、そのほとんどで病院が刑務所、それも古風な地下牢じみた刑務所と同じようなものとして扱われていることに気がつくだろう。病院は腐敗と苦痛と死の場所であり、墓地への控えの間のようなものだった。貧窮者でもなければ治療を求めてそんな場所に行こうとは思いもしなかっただろう。とりわけ前世紀の初め頃、医療科学が以前よりも大胆になっていき、しかし何も成果が得られていなかった時期には医者のおこなうこと全てが一般の人々から恐怖と嫌悪の目で見られていたのだ。中でも外科手術は身の毛もよだつようなサディズムの一形態としか思われていなかったし、死体泥棒の助けを借りなければなし得なかった解剖は黒魔術と混同されることさえあった。十九世紀の作品からは医者や病院にまつわる膨大な数のホラー作品を集めることができるだろう。「失神するまで血を流させよう」とする外科医たちを見て慈悲を乞う金切り声をあげる痴呆に侵された哀れな老ジョージ三世を想像してみるといい! パロディーとも思えぬようなボブ・ソウヤーとベンジャミン・エイリアンの会話を、あるいは壊滅や戦争と平和に出てくる野戦病院、メルヴィルの白いジャケツで描かれる切断手術の衝撃的な描写を! 十九世紀のイギリスの創作では医者にはスラッシャー(切り裂き魔)、カーバー(肉切り人)、ソーヤー(のこぎり引き)、フィルグレイブ(埋葬人)といった名前が付けられることさえあったし、よく使われるあだ名は「骨切り人」だった。それらは彼らの滑稽さと同じくらいその不気味さに由来したものだろう。外科手術を嫌う伝統をもっともよく表しているのはおそらくテニスンの詩、小児病院小児病院:オーウェルは「小児病院(The Children's Hospital)」としているが正確には「小児病院にて(In the Children's Hospital)」だろう。比較的新しい一八八〇年頃に書かれたものであるにも関わらず、この作品は本質的にはクロロホルム麻酔以前の時代に属している。さらに言えばテニスンがこの詩に遺しているものの見方にもまさに同じことが言える。麻酔無しでの手術がどんなものにならざるを得なかったか、それがどれほど悪名高いものだったかを考えれば、そのようなことに手を染めようとする人間の動機に疑いの目を向けないでいることは難しいだろう。学生たちが切望する(「スラッシャーが動き出したら最高の見物だ!」)これら血塗られた戦慄がおおよそ無意味なものであることは明らかだ。ショック死を免れた患者も普通は壊疽によって死に、その結果は当たり前のこととして受け取られる。現在でさえ、その動機に疑問符がつく医者は見つけ出すことができる。重い病気にかかったことがある者や医学生の会話を耳にしたことがある者であれば私が言っている意味がわかるだろう。しかし麻酔が転換点となった。また消毒剤もそのひとつだろう。今ではアクセル・ムンテによって描かれたサン・ミケーレ物語に登場するような場面を目にできる場所はおそらく世界中を探しても見つからない。シルクハットとフロックコートを身に着け、糊のきいたシャツの胸には血と膿が飛び散っている邪悪な外科医が同じメスを使って患者を次から次に切り刻んでは切断した手足を脇のテーブルに放って積み重ねるという光景は存在しないのだ。さらに言えば国民健康保険によって、労働者階級の患者は注意を払う価値のない貧窮者であるという考えは部分的には取り除かれた。今世紀に入ってもしばらくの間、大きな病院の「無料」患者は麻酔無しで抜歯をおこなうのが普通だった。支払いをしていないんだ、なんだって麻酔をかけてやらなくちゃならないんだ……そういう姿勢だったのだ。これもまた変わった。
しかしそれにも関わらず、公共の施設にはまとわりついて離れない過去の記憶がいつまでも残り続けることだろう。兵舎の部屋にはいまだにキプリングの亡霊がとりつき、救貧院に足を踏み入れればオリバー・ツイストを思い出さずにはいられない。病院はハンセン病患者や死にゆく者の収容所として誕生し、医学生が貧者の体で技術を学ぶための場所として続いてきた。その特徴的な陰鬱とした建物からその歴史のかすかな名残を見て取ることができるだろう。そこがどこであれイギリスの病院で受けた治療について不満を言おうというつもりは私には毛頭ないが、病院、とりわけ病院の大部屋にはできる限り関わり合いになるなと私が警告しているように聞こえるだろうことは理解している。「規則を受け入れるか、さもなくば出ていくか」という状況では、どのような法的見解に立ったところであなた自身へどのような治療が施されるかにはたいして口出しできないし、無根拠な実験があなたに試みられない保証がないことは疑いない。そして自宅のベッドで死ぬということはすばらしいことだ。健康なまま突然の死を迎えられればさらにいい。その多大なる配慮と効率の良さにも関わらず、病院での死にはどこか残酷で、行き届かないところがある。おそらくあまりにかすかなために声に出しては語られない恐ろしげな苦痛の記憶を背後に残した何かが、見知らぬ人々の中で毎日のように人間が死んでいく場所の持つ落ち着きのなさ、人の多さ、非人間性から生み出される何かがあるのだ。
おそらく病院に対する恐怖は極度の貧困にある人々の間にはいまだに残っているはずだし、それが私たちの間から消えたのはつい最近のことだ。それは私たちの表層意識からそう深くないところにある暗闇の一画なのだ。とある病院の病室へ足を踏み入れた時、奇妙な懐かしさを感じた、と先に私は言った。私の頭に浮かんだのは十九世紀の悪臭と苦痛で満ちた病院、目にしたことはないが語り継がれた知識として知るそれだったのだ。そして薄汚い鞄を持った黒衣の医者か、不快な臭いかのなにかしらが、二十年の間、私の頭に浮かぶことの無かったテニスンの詩、小児病院を私の記憶から掘り出すという奇妙な芸当を演じて見せたのだ。私が子供だったころ、それを読み聞かせしてくれたのはテニスンがその詩を書いた時代からその職についているであろう看護師だった。古い時代の病院の持つ恐ろしさと苦しさの記憶は彼女にとって鮮明なものだっただろう。私たちは一緒になってその詩に身震いしたが、その後、それは私の記憶から消え去っていた。その名前を聞いてもおそらく私は何も思い出しはしなかっただろう。しかしベッドがひしめく、薄暗いざわめきに満ちた部屋をひと目見て、唐突にそれに関する一連の物事が思い出されたのだ。そしてその晩、私はあの詩の筋書きとそれが持つ雰囲気をその一行一行のほとんどとともに思い出したのだ。