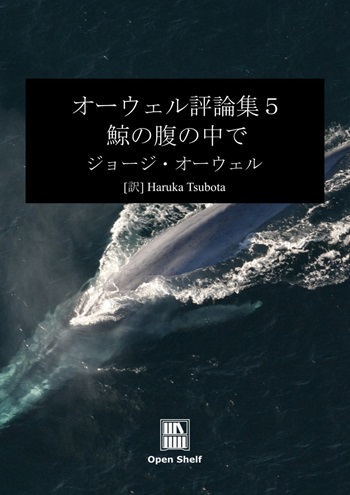第一章
あらゆる身体的記憶の中で最初によみがえるのは音、匂い、そして物の外観である。
スペイン戦争の後、何よりも鮮明に思い出せるのが前線に送られる前に受けたいわゆる新兵訓練の一週間であるのは興味深い……バルセロナの大きな騎兵用兵舎には隙間風の吹く馬小屋と丸石を敷き詰めた囲い地があった。洗濯場のポンプの氷のような冷たさ、ブリキのコップに入れられたワインでなんとか耐えた不潔な食事、薪を割るズボン姿の女性民兵たち。早朝の点呼では私のありきたりなイギリス的名前が、マニュエル・ゴンザレス、ペドロ・アギラル、ラモン・フェネロッサ、ロケ・バラスター、ジェイム・ドメネク、セバスチャン・ヴィルトン、ラモン・ヌーヴォ・ボッシュといった轟くようなスペイン的名前の間である種の滑稽な間奏となった。私がこうした特定の男たちの名を挙げられるのは彼ら全員の顔を憶えているからだ。今頃は間違いなく良きファランヘ党員ファランヘ党:スペインの政党。1937年にナショナリスト派と合流した。になっているであろう人間のクズである二人を除けば、おそらく彼らは全員死んでいる。彼らのうちの二人が死んだことは私も知っている。最年長の者は二十五歳くらい、最年少の者は十六歳だったはずだ。
戦争で必ず経験することのひとつは人間の発する不快な匂いから逃れようとして決して逃れられないことである。便所は戦争文学で擦り切れるほど取り上げられている題材なので、もし私たちの兵舎の便所がスペイン内戦に対する私自身の幻想をしぼませるという欠かざる役目を果たさなかったら私もそれについて話をしようとは思わなかっただろう。しゃがんで用を足さなければならないラテン式の便所はどうやってもひどいものにならざるを得ないが、そこは何かなめらかな種類の石でできていて誰も立っていられないほど滑りやすかった。加えて常に詰まるのだ。今も記憶には不快なものが十二分に残っているがまず最初に頭に浮かぶのはこの便所のことで、繰り返し思い出す。「革命軍の兵士としてここに自分たちがいるのはファシズムから民主主義を守るため、何事かに関する戦争を戦うためだが、その生活の中身といえばブルジョアの軍隊はおろか、まるで刑務所にいるかのように不潔でみっともない」。後になるとこうした印象は他の物事、例えば塹壕生活での退屈と動物的飢え、残飯をめぐる卑しい悪巧み、睡眠不足で疲れ切った人々がふける慢性的な言い争いによっても強くなっていた。
軍隊生活で避けることのできない恐怖(兵士だったことのある者であれば誰でも「軍隊生活で避けることのできない恐怖」という言葉で私が何を指しているのかわかるだろう)はその時に参戦している戦争の性質にはほとんど影響を受けない。例えば規律は全ての軍隊でまったく同じである。命令には従わなければならず、必要であれば罰によってそれが強制される。将校と部下の関係は上位者と下位者の関係でなければならない。西部戦線異状なしといった書籍で説明される戦争の実態はだいたいにおいては真実である。銃創、死臭、銃撃戦に巻き込まれた男たちはしばしばズボンを濡らすほど怯える。軍隊を生み出す社会的背景がそこでの訓練、戦術、全体的な能率に影響を与えることは確かだし、また自分たちの側に正義があるという意識が士気を高めることも間違いない。とはいえこの効果は軍隊よりも一般市民の方が大きい(人々が忘れがちなのは、それがどこであれ前線の近くにいる兵士は普通、空腹や怯え、寒さ、とりわけ退屈によってその戦争の政治的原因について思い悩もうとはしなくなっているということだ)。しかし自然法則は「赤」軍に対しても「白」軍と同じように容赦しない。たとえその時に戦っている原因について正当性があろうがシラミはシラミであり、爆弾は爆弾である。
これほど明白であることを指摘するのはなぜか? それはイギリスとアメリカの知識人の大部分は当時も今も明らかにこうしたことに無知であるからだ。昨今、私たちは物忘れが激しいが、少し振り向いてニュー・マッセズ誌ニュー・マッセズ誌:アメリカの共産主義系文学雑誌やデイリー・ワーカー紙デイリー・ワーカー紙:アメリカの共産党の機関紙を掘り返し、私たち左派が当時吐き出していたロマン主義的な戦争挑発の汚物を見てみることだ。なんと陳腐で古臭い文句! そしてその想像力に欠けた無神経さ! マドリードの爆撃を眼前にしたロンドンの平静さ! 私はここで右派、ランラン:アーノルド・ラン。イギリスの作家、スキー選手、登山家。スペイン内戦ではナショナリスト派支持を表明した。、ガーヴィンガーヴィン:ジェームス・ルイス・ガーヴィン。イギリスのオブザーバー紙の編集者、ジャーナリスト。といった反対側のプロパガンダの担い手についてどうこう言うつもりはない。彼らには何を言っても無駄だ。しかし二十年の間にわたって戦争の「栄光」、残虐な物語、愛国心、さらには肉体的勇敢さをやじり、嘲っている人々がいたのだ。彼らはほとんど変わることのない顔ぶれで一九一八年のデイリー・メール紙がお似合いであろう内容を発表し続けていた。イギリスの知識人たちが熱心に取り組んでいることがひとつあるとすれば、それは戦争に対する考え、つまり戦争とはまさに死体と便所であって、なんら好ましい結果をもたらすことは無いという理論を反故にすることだ。例えば一九三三年には、特定条件下で自分は自国のために戦うと言われて憐れむように冷笑していたのと同じ人々が、一九三七年には、負傷したばかりの男たちが戦いに戻っていると主張するニュー・マッセズ誌の記事は誇張だと言われて相手をトロツキー主義のファシストと非難していたのだ。左派の知識人たちは矛盾を感じ無いばかりかほとんど何の移行段階も踏まずに「戦争は地獄」から「戦争は栄光」へと自らの方向を転換したのだった。後に彼らの多くは同じくらい強烈な別の変化を見せた。いわば知識人の中核である実に多くの人々が一九三五年には「王と国家」宣言「王と国家」宣言:1935年となっているがおそらく1933年にオックスフォード大学のディベート部でおこなわれた「王と国家」議論(The King and Country debate)を指しているものと思われる。に賛成し、一九三七年にはドイツに対する強硬姿勢を叫び、一九四〇年には人民会議を支援し、現在では第二戦線第二戦線:第二次大戦でイギリス、アメリカによってノルマンディー上陸後に開かれた対ドイツ戦線のことを要求している。
人々の大半の振る舞い、つまり昨今起きているその途方もない意見の転換やタップダンスのように沸いたり止んだりする感情について言えばそれは新聞とラジオによる催眠の結果だ。知識人に関して言えば彼らは結局のところ金銭とたんなる肉体的安全に終始していると言わざるを得ない。時に応じて彼らは「主戦」にも「反戦」にもなろうが、どちらの場合でもその頭の中に戦争の現実的イメージを持ち合わせてはいない。もちろんスペイン戦争に熱狂していた時の彼らは人々が殺されていることも、それが好ましくないこともわかっていたが、彼らはスペイン共和国軍の兵士にとって戦争の体験はどうしたわけか下劣なものではないのだと強く感じていた。どうしたわけか便所の悪臭は薄れ、規律はうんざりするものでなくなるというわけだ。ニュー・ステーツマン誌を一目見るだけで彼らがそう信じていたことがわかる。現在、まさにそれと同じようなナンセンスが赤軍について書かれている。明白な事実を理解できなくなるほど私たちは文明化されてしまったというわけだ。真実は極めてシンプルなものである。生き残るためにはしばしば戦わなくてはならない。そして戦うためには自身を汚す必要があるのだ。戦争は邪悪なものだが、それでもまだましであることがよくある。剣を手にした者たちは剣によって滅び、剣を手にしなかった者たちは悪臭を放つ病によって滅びる。こうした決まり文句には書き留めておくだけの価値があるという事実はレンティア資本主義下の日々が私たちに何を成したかを示している。