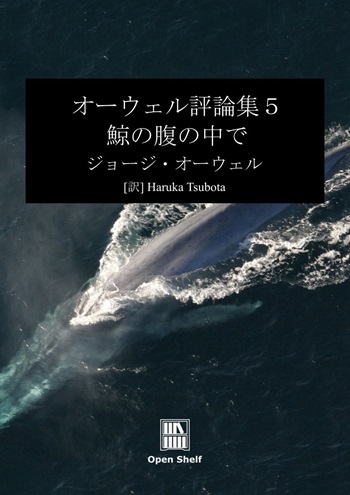マーク・トウェイン―公許の宮廷道化師
トム・ソーヤとハックルベリー・フィンだけとはいえマーク・トウェインはエブリマンズ・ライブラリーのそびえ立つ門扉に押し入り、「児童書」を装った(しかしそうではない)これら作品によってすでに広く知られている。彼の最高の、そして最も特徴的な作品である西部放浪記、イノセント・アット・ホーム、ミシシッピの生活はこの国でもいくらかは記憶されているが、アメリカではあらゆる場面で文学的意見に混ざり込む愛国心によってそれら作品が生命を保っていることは間違いない。
マーク・トウェインはジャンヌダルクのいやに感傷的な「生涯」から、決しておおやけに出版できないようないかがわしいパンフレットにまで及ぶ驚くほど多彩な作品を生み出しているが、彼の作品の中でも最高のものはミシシッピ川と西部の荒涼とした鉱山街についてのものに集中している。一八三五年に生まれた(ひとりか二人の奴隷を所有できるほど裕福な、南部の家庭の出身である)彼がその青年期と成人期初期を過ごしたのはアメリカの黄金時代、大平野が開けて富とチャンスが無限かと思え、人類が自由を感じ、また確かに自由だった時期、これまでになく、これから先も何世紀かはないであろう時期だった。私が先に述べたミシシッピの生活と他の二冊は真面目かつ風刺的な説話、風景説明と社会史の寄せ集めだがそこには中心的テーマがあって、それはおそらく「これこそが解雇に怯えていない時の人間の振る舞いだ」という言葉に要約できるだろう。これらの作品の内容に関して言えばマーク・トウェインは自由への賛歌を自覚的に書いているわけではない。第一に彼が関心を持っているのは「人間性」であり、経済的圧力と慣習の両方が取り除かれた時に人間がとり得る風変りな、ほとんど狂的ともいえるその多様性なのだ。彼の描くいかだ乗り、ミシシッピの水先案内人、鉱山労働者、無法者はおそらくそれほど誇張されたものではないが、そのどれをとっても中世の大聖堂のガーゴイルと同じくらい現代の人間と異なっている。彼らは風変りで、時に邪悪な個性を発達させているがそれは外部からの圧力のまったくの欠如によるものだ。こうした状態はめったに存在しない。教会は弱体化し多くの声に邪魔立てされ、土地は手に入れ放題だ。もし仕事が気に入らなければ上司の顔面を殴りつけて、西の遠くへ引っ越せばいい。さらに金は十分にあって流通している一番小さいコインが一シリングほどの価値がある。アメリカの開拓者はスーパーマンではないし、特に勇敢というわけでもなかった。忍耐強い金鉱掘りの町全体が公共心の蓄えに欠けた無法者によって脅かされるがままになっていた。また階級区別から自由であるというわけでもなかった。デリンジャー拳銃をベストのポケットにいれて二十人殺したことを自慢する、鉱山の集落の通りを闊歩するならず者がフロックコートと光沢のあるシルクハットを着こんで自分を「紳士」だと断言し、テーブルマナーに口やかましくしていた。しかし少なくとも人の運命が生まれた時から決まっているというわけではなかった。未開拓の土地が残っている間は「丸太小屋からホワイトハウスへ」の神話は真実だったのだ。ある意味でパリの群衆がバスティーユ監獄を襲撃したのはこのためだったが、マーク・トウェインやブレット・ハート、ホイットマンを読むとその努力も無駄ではなかったと感じる。
しかしマーク・トウェインはミシシッピやゴールドラッシュの年代記編纂者以上の存在になることを目指していた。生きていた当時、彼はユーモア作家、そして愉快な講演家として全世界にその名をはせていた。ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、ウィーン、メルボルン、カルカッタで膨大な数の聴衆が、今ではほとんど例外なく面白みを失ったジョークに体を揺すって笑い転げたのだ(マーク・トウェインの講演が成功を収めたのはアングロ・サクソンとドイツの聴衆に対してだけだった点を指摘しておくことには価値があるだろう。比較的成熟したラテン人種……彼が主張するところではその独自のユーモアは常にセックスと政治の周りを巡っている……からはまったく関心を持たれなかったのだ)。しかしそれに加えてマーク・トウェインは社会評論家、さらにはある種の哲学者であるという自負さえも持っていた。彼は自らの中に因襲打破的、さらには革命家的性質を持っていて、彼は明らかにそれを追求したいと欲しながらも、しかしどうしたわけか決してそれを追求することはなかった。彼は迷妄の撲滅者、民主制の主唱者になれただろうし、健全で愉快であった分、ホイットマンよりもずっと重要な人物になれたことだろう。しかし代わりに彼は入国審査官におだてられ、王族に歓待されるうさんくさい「著名人」になった。その経歴は南北戦争の後に始まったアメリカの生活の退廃を反映している。
マーク・トウェインはときおり同時代者であるアナトール・フランスと比較される。この比較はあながち的外れなものではない。両者ともヴォルテールの精神的末裔であり、両者とも人生に対してアイロニカルで懐疑的な考えを持ち、生まれつきの悲観主義を陽気さで覆い隠している。両者とも既存の社会秩序が不正なもので、そこで重要とされている信念のほとんどが妄想であることを知っている。両者とも強硬な無神論者で、この宇宙の耐え難い残酷さを確信している(マーク・トウェインの場合にはこれはダーウィンによっておこなわれた)。しかし似ているのはそこまでである。両者のうちのフランス人の方がずっと博学で洗練されていて、審美的に生き、さらにはずっと勇敢なのだ。彼は自分が疑いを抱くものに攻撃を仕掛け、マーク・トウェインのように「著名人」や公許の宮廷道化師の愛想のいい仮面の後ろに隠れたりはしない。彼には教会の怒りを買う危険を犯したり、論争……例えばドレフェス事件……で評判の悪い側につく用意がある。マーク・トウェインは……おそらく「人間とは何か?」という短いエッセイのひとつを除けば……広く認められている信念に対して、自らを厄介事に巻き込みそうなやり方で攻撃を仕掛けたりは決してしない。そしてまた、成功と善は同じものであるというおそらくはアメリカに特有な観念から自らを引き離すことも決してできないだろう。
ミシシッピの生活にはマーク・トウェインの性格の重要な弱点を描き出す奇妙で些細な部分がある。このおおまかには自叙伝的な作品の序盤でその日付けが書き換えられているのだ。マーク・トウェインはミシシッピの水先案内人としての自身の冒険を当時十七歳ぐらいの少年だった自身が体験したもののように描いているが、実際には彼は三十近い青年だったのだ。これには理由がある。この作品の同じ部分には南北戦争での自身の手柄が書かれているが、これは間違いなく恥ずべきものだ。もっと言えばマーク・トウェインは最初は南軍の側で戦い……彼が戦ったと言えればだが……その後、戦争が終わる前に忠誠の対象を変えている。こうした振る舞いは成人よりも少年である方が許されやすく、そのために日付けの調整がおこなわれたのだ。しかしまた彼が付く側を変えたのは北軍が勝つことを見越してのことだったことも十分、明らかである。そしてこのいつでも可能な限り強者の側に付き、そちらにこそ正義があると信じるというこの傾向は明らかに彼の経歴全体を通して言えることなのだ。西部放浪記にはスレイドという名の無法者に関する興味深い説明がある。無数の暴挙ととりわけ二十八件の殺人を犯したことで知られる男だ。マーク・トウェインがこの吐き気をもよおす悪党に感服していることは完全に明らかである。スレイドは成功者であり、従って彼は感服に値する。こうした現在でも広く見られる考え方は重要なアメリカ的表現である「うまいことやる」という言葉に要約される。
南北戦争後の金儲けの時代にはマーク・トウェインのような気質の者にとって成功者になることを拒否するのは難しいことだった。エイブラハム・リンカーンに代表される昔ながらの素朴な、木彫りと噛みタバコの民主主義は死に絶えようとしていた。今や安価な移民労働者と成長する大企業の時代となったのだ。マーク・トウェインは穏やかな調子で金メッキ時代の同時代人を風刺したが、彼自身も広がる熱病におかされて膨大な額の金を稼いでは失った。彼は何年かの間、商売のために著作を止め、道化を演じて時間を浪費することさえした。講演旅行や一般向け晩餐会だけではなく、例えばアーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキーのような作品を書くこともそうだ。この作品はアメリカの生活における最低で最も粗野なもの全てに対して意図的におこなわれたお追従に他ならない。言ってみれば丸太小屋のヴォルテールになれたであろうこの男は世界有数の夕食後の講演家になり、自身の小話そっくりな魅力と実業家に自らを公共へ資する慈善家だと感じさせる力を手にしたのだ。
マーク・トウェインが書くべき作品を書くのに失敗した責任は彼の妻にあると一般に言われ、彼女が彼に対してひどく支配的に振る舞っていたことも明らかになっている。毎朝、マーク・トウェインは自分が前日に書いたものを彼女に見せ、クレメンス夫人(マーク・トウェインの本名はサミュエル・クレメンスである)は青い鉛筆を手にそれを調べて不適切だと思う部分を全て削除したのだ。十九世紀の基準から見ても彼女は苛烈な検閲官だったようだ。W・D・ハウエルズの著作である我がマーク・トウェインにはハックルベリー・フィンに紛れ込んだひどい罵り言葉を巡って引き起こされた騒動についての記述がある。ハウエルズによればマーク・トウェインはそれこそが「まさにハックが言うであろうこと」だと認めながらも、その言葉は印刷できるようなものではないというクレメンス夫人に同意したのだ。そしてその言葉とは「ちくしょう」なのだ。とはいえ真に自分の妻の知的奴隷であるような作家はいない。クレメンス夫人もマーク・トウェインが本当に書きたいと思っている本の執筆を止めることはできなかった。彼女は彼が社会に降参しやすくはしてやっただろうが、この降参は彼自身の性格が持つ欠点、成功を軽蔑できないことによって起きたものだった。
マーク・トウェインの作品のいくつかは必ずや生き残っていくだろう。そこには計り知れないほど価値のある、社会の歴史が含まれているからだ。彼の人生はアメリカが拡大していく偉大な時期と重なっている。彼が子供だった頃にはピクニック用の弁当を持って奴隷廃止論者の絞首刑を見物に行くのはごく普通のことであり、彼が死んだ頃には飛行機は目新しいものではなくなっていった。この時期、アメリカで生み出された文学作品は比較的少なく、マーク・トウェインがいなければミシシッピの外輪船や平野を行き交う駅馬車についての私たちのイメージは今よりもずっとぼんやりしたものになっていたことだろう。しかし彼の作品を研究した人間のほとんどは彼にはもっとすばらしいことができたのではないかという気持ちを抱くことだろう。彼からは、何かを言いかけてそれに尻込みしているような奇妙な印象を常に与えられる。ミシシッピの生活やその他の作品にはもっと偉大でずっと首尾一貫した作品の亡霊がつきまとっているように思えるのだ。彼が自分の自叙伝を、人間の精神生活は言葉で言い表せないものであるという発言で始めたのは重要である。彼が何を言おうとしたのか私たちにはわからない……入手不可能なパンフレットである一六〇一一六〇一:エリザベス一世の侍女の日記という体裁でエリザベス一世と当時の著名な作家の会話を描いたマーク・トウェインの作品。扇情的な内容で知られる。始めは匿名で出版されたが後に著者がマーク・トウェインであることが明らかにされた。からは手がかりを得られる可能性があるが、推察するにそれは彼の名声に大きな損害を与えてその収入のかなりの部分を減らすものなのだろう。