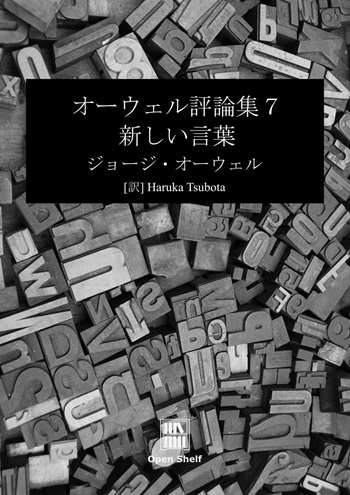書評 ランスロット・ホグベン著「インターグロッサ」、コンプトン・マッケンジー著「ミスター・ルーズベルト」
ホグベン教授は自身の興味深い短い書籍に「言語設計へ意味論的原理の適用を試みる、民主的世界秩序のための補助言語についての草稿」という副題をつけているが「草稿」という語には強調が必要だ。
インターグロッサは新しい言語である――ホグベン教授自身の発明品だ。しかし彼はそれを既製品として世界に押し付けようとはしていない。ただ「議論の叩き台」として提示しているだけだ――前提となっているのは今回の戦争が終わった時には十分に満足のいく国際言語が作り上げられるだろうということである。
世界共通の第二言語を最終的に全世界で採用する場合にはそれは国際的な専門家集団によって作り上げられなければならないと彼は考えていて、おそらくこれは正しい。
これまでよく起きていたのは誰かが新しい言語を発明し、他の誰かが「そいつを改善できる」と言い出し、もしそれらが使われれば、そのでっち上げられた言語が自然言語のものよりもひどいバベル的混乱を作り上げるまでこの過程が続いていくことだった。
すでに三百以上の人工言語が存在し、(ベーシック英語ベーシック英語:イギリスの言語学者のチャールズ・ケイ・オグデンによって考案された人工言語。850語の基礎語から構成される。を別にしても)そのうちの五つ、六つほどは今でも多かれ少なかれ使われている。
インターグロッサは中国語のように完全な「孤立語」言語「孤立語」言語:語が独立していて語尾変化(屈折形)が無く、意味が語順によって決まる語。中国語やタイ語などが代表的。だ。その単語は何ら語尾変化せず、意味は文章の順序と時制を表わすわずかな数の「空白」語などによって示される。
この優位性はもちろん非常に大きい。語尾変化のない言語は習得が比較的容易で、とりわけ語尾変化の無い言語を話す数億のアジア人にとってはそうだ。
また絵によって初心者に教えるのも容易だ。この書籍にはいくつかの例が挙げられている。例えば、二人の赤い人間が中にいる黒い家の絵には「bi erythro homini in melano domi」と説明が書かれている一方で正面に二本の黒い木がある赤い家には「bi melano dendra antero erythro domi」と説明が書かれている。わずかな語尾変化しかしない英語はおそらく別として、ヨーロッパ系言語にこうした方法を使うことは難しいだろう。
インターグロッサの語彙はラテン語とギリシャ語に基づいている――おそらくギリシャ語の方がわずかに多い。この理由はホグベン教授が、可能な限り現在すでに国際的に通用する単語を使っていて、そのほとんどが科学と技術の用語であるためだ。
教育が普及している世界のほとんど全てで、photo、phono、ptero、graph、geo、microといった語根の意味はすでによく知られていて、インターグロッサの単語は利用できる時には常にそうしたものを基礎にしている。教育を受けたヨーロッパ人であれば誰もが、また教育を受けたインド人や日本人のおそらくほとんどがインターグロッサの単語「hydro」が何か水に関係していることをひと目で理解するだろう。
その語彙は主に単語の経済性を考慮して作り上げられている。ホグベン教授によれば七百五十語もあれば十分なのだそうで、これはベーシック英語で必要とされるよりも少ない数である。
記憶力の良い者であれば誰でもおそらく数週間以内に習得でき、ラテン語とギリシャ語を学んだ者であれば誰でもインターグロッサの多くの文章を見てすぐに意味を推測しながら読み進められるだろう。
さて、インターグロッサの優位性のいくつかを示してきたが、それではなぜ私はこの言語の将来性を信じていないのだろうか。そう、もちろんのことだが私は信じていないのだ。
まず、仮に賛同できるものであってさえ、人工言語が既に何億もの人々によって話されている言葉に対抗して普及するとは信じ難いことが挙げられる。
ホグベン教授の一番の対抗者はもちろんベーシック英語だ。おそらくベーシック英語はインターグロッサよりもわずかに習得が難しいが、実のところそれへ反対する唯一の論拠は多くの人々の脳裏に浮かんで離れないある疑い、すなわちそれがアングロアメリカ帝国主義の道具なのではないかという疑いなのだ。
それを補うのが二、三億人の人々と即座に意思疎通ができるというとてつもなく大きな優位性である。さらにベーシック英語から標準英語へと進むことを選んだ者は誰でも世界規模の報道や数百年分の文学を利用できる。
話者の多いいくつかの自然言語についても同様である。人工言語にはこうした優位性が全く無い。独自の技術的文献でさえそれを手にできるようになるまでには何年もの翻訳作業が必要になるだろう。
これ以上の批評についてはおそらくインターグロッサを学んでからでないとすべきではないのだろうがあえてしよう。それは、厳密に技術的な目的の場合は別にしてもホグベン教授は言語を創出する上で適切な人物なのか非常に疑わしいということだ。
英語についての彼の文章は、彼が言語に対して何の感情も持っていないことを示唆している。耳の聞こえない者が音楽に対して持つ感情よりもなお少ない。彼の前書きから二つの文章を引用するだけで十分だろう。
“The conclusion is dubious if we give due weight to what has been a powerful motive militating against Peano's radical attitude to superfluous flexions of the type characteristic of Aryan languages.”
(アーリア語群に特徴的な型の過剰な語尾変化へのペアノの急進的態度へ作用する強力な動機となったものへ相応の重要性を与えるならばこの結論は疑わしい)
“We cannot play ducks and drakes with a native battery of idiom which prescribes such egregious collocations of vocables as the Basic ‘put up with’ for ‘tolerate’ or ‘put at a loss’ for ‘bewilder.’ ”
(「tolerate」(耐える)の代わりに「put up with」(我慢する)を、「bewilder」(当惑させる)の代わりに「put at a loss」(迷わせる)を基礎に置く、こうした実にはなはだしい語の集合を処方するような天然の慣用句の一群を湯水のように使うことは私たちにはできないのだ)
自身の母語でこのようなものを書く人々は新しい言語の創出者としては信用しにくい。
もちろん国際言語は文学的目的のために考案されているわけではないが、もしそれらがホグベン教授が正しくも恐れているナショナリズムに対する武器として使われるのであれば、たんなる技術や科学のジャーゴンであってはならないはずだ。それらは最大限の明瞭さで極めて微妙な意味合いを表現できなければならないが、そうであればそれは真に明瞭さに配慮する者、例えば「egregious(はなはだしい)」という語の意味を労を取って調べようとする者によって考案されるべきなのだ。
それでもやはりこれは実に刺激的な書籍であり、また重要な書籍でさえある。たとえインターグロッサが決して採用されることも、あるいは他の言語の土台としてさえ使われることがなくとも、全世界的コミュニケーション媒体の緊急の必要性や、いくつかの現代語が帝国主義の目的のために使われているその邪悪な手口へ注意を向けさせるものは何であれ歓迎されるべきである。
八千語からなる英インターグロッサ辞書がこの導入的な巻に続いて出版される予定だ。
ルーズベルト大統領は現在に至ってもイギリスの人々にはあまりよく知られていないが、マッケンジー氏が私たちに提示した書籍はとうていルーズベルト大統領にふさわしいものとは言えない。大急ぎで書かれたもののように見え、その誕生から事細かな事実を積み上げていっているにも関わらず(実のところ、有力な血縁を持つほとんどの人々と同様、ルーズベルト氏の青年時代にはたいした出来事は起きない)平均的なイギリスの読者にはアメリカ政界の理解可能な図式を与えないだろう。
部外者から見るとアメリカ政治は謎に包まれているがマッケンジー氏はその謎をほとんど解き明かしていない。また彼は英雄崇拝に傾き過ぎている。ルーズベルト大統領は偉大な人物でイギリスの良き友だが、それだけに彼が権力の座に長く留まればそれだけ得るものの多いイギリスの人々は彼のもっと批評的人物像を手にするべきなのだ。
この書籍から何とかわかるのはルーズベルト氏にも普通の人間が持つ欠点がいくらかあることだけであり、彼に対抗して強力で邪悪な力が結集していることはわからないだろう。この書籍で最も評価できるのは大部分が写真からなる興味深い図画で、おそらくそれで価格の元は取れる。