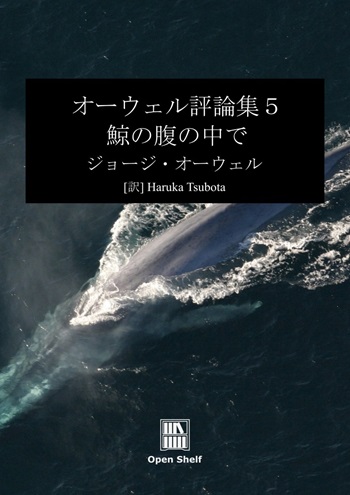ラドヤード・キップリング
このキップリングの詩選集の序文として書かれた長いエッセイでエリオット氏がひどく弁解がましい態度を強いられているのは残念なことだ。しかしそれは避け難いことでもある。キップリングについては口に出す時でさえ、彼の作品を読んだことのない二種類の人々が作り出した伝説を否定することから始めなければならないのだ。キップリングは過去五十年の間の類型として特有の位置を占めている。文学の五つの世代の間、見識ある人物の誰もが彼を侮っていたが時代が過ぎてみればそれら見識ある人物の十人のうち九人までが忘れ去られ、それでもなおキップリングは何らかの形で存在し続けている。この事実についてエリオット氏は満足のいく説明をまったくしていない。キップリングは「ファシスト」であるという浅はかでおなじみの非難に対する返答で擁護不可能な見地から彼を擁護するという正反対の過ちを犯しているのだ。キップリングの人生観は全体的に見れば文明的な人間にとっても受け入れられる、あるいは許容できるものであると装うのは無益なことだ。例えばイギリスの兵士が金銭を取り上げるために「ニガー」をクリーニングロッドクリーニングロッド:銃の銃身を掃除するための道具で殴りつける様子をキップリングが描く時、彼はたんに記録者として振る舞っているだけで自分の描いているものに必ずしも賛成しているわけではない、と主張するのは無駄だ。こうした種類の振る舞いに対する不賛意はキップリングの作品のどこを探しても微塵も見つからない……反対に、彼には明白なサディズム的傾向があり、それはこうしたタイプの作家がやむなく持たざるを得ない残虐性を上回るものだ。キップリングは好戦的・自国優越的な帝国主義者であり、道徳的には欠落し、審美的には不快な人物である。まずはじめにそれを認め、その後に、彼を冷笑する上品な人々がまったく消え去ったように思える一方で彼が生き残っているのはなぜなのかを理解することに取り組んだ方がいい。
しかしそうであっても「ファシスト」という非難には答える必要があるだろう。道徳的にであれ政治的にであれキップリングについて何らかの理解を得る最初の手がかりは彼がファシストではないということにあるからだ。現代の最も人道的、あるいは最も「進歩的」な人物よりもなおいっそう彼はそれからかけ離れていた。その文脈を調べたり意味を考察したりをまったく試みずに、あちらこちらからそのまま抜き書きしてみた時に興味深い一例であるのが「退場賛美歌」からの一節、「法を持たぬ劣等種」である。この一節は気取った左派の内輪では決まって冷笑の的となる。当然のことながらこの「劣等種」は「原住民」であると見なされ、呼び起こされるイメージは探検帽を被って苦力を蹴りつけるご立派な主君である。しかし文脈の中に置かれた時、この一節が意味するものはそれとほとんど正反対と言っていいものなのだ。「法を持たぬ劣等種」というフレーズが指しているのはまず間違いなくドイツ人、とりわけ汎ゲルマン主義の作家たちであり、無力という意味ではなく無法という意味での「法を持たぬ」者なのだ。この詩全体は普通は熱烈な大言壮語であると考えられているが、実のところ武力外交、イギリス、そしてドイツへの糾弾なのだ。二つの連は引用しておく価値があるだろう(私はこれを詩としてではなく、政治的なものとして引用している)。
力を見て酔えば我ら堕落す
畏敬の念抱く汝を持たぬ野蛮なる言葉、
異邦人の使うがごときその驕りの言葉、
あるいは法を持たぬ劣等種……万軍の神、いまだ我らと共にあり
我ら忘るまじ ……我ら忘るまじ!
彼女の所望する異教徒の心臓のため
硫黄の匂い放つ銃身と鉄の弾丸
遺骸の上に積まれし全ての勇猛なる遺骸
そして衛兵、守るべき汝を呼ばず
狂乱した驕りと愚かさのため……汝の民への汝の慈悲、ああ主よ!
キップリングの用いている表現の多くは聖書から取ってきたもので、二番目の連で彼の念頭に置かれているのが詩編第百二十七番の文句「主が家を建てられるのでなければ、建てる者の労働はむなしい。主が町を守られるのでなければ、夜警が目覚めていようともむなしい」であることは疑いない。ヒトラー以後の人間の頭にはあまり響かない文句である。現代では軍事力よりはるかに勝る制裁が存在すると信じる者は誰もいない。より巨大な力を用いること無しに力に打ち勝つことができると信じる者は誰もいない。「法」は存在せず、ただ力だけが存在するのだ。私はそれが正しい信念だと言っているのではない。ただ、それこそが現代人の全てが実際に強く信じている信念であると言っているだけだ。そうでないふりをしている者たちは知的臆病者か、軽薄な偽装の下に隠れた権力崇拝者か、あるいはたんに自らが生きる時代に取り残されているかのどれかだ。キップリングの物の考え方はファシスト以前のそれである。彼は、敗北を前に誇りを抱くこと、そして神々が思い上がりを罰することをいまだ信じているのだ。戦車や爆撃機、ラジオや秘密警察、それらがもたらす精神的結果について彼は予見してはいない。
しかしこうした指摘は、キップリングの好戦的自国優越主義と残忍性について私が先に述べたことを取り消すものになるのだろうか? それは違う。たんに十九世紀の帝国主義者の物の考え方と現代の悪党の物の考え方は二つの異なるものであるというだけの話なのだ。キップリングは一八八五年から一九〇二年という期間に絶対的に属している。第一次世界大戦とその影響は彼を苦しめたが、それでもボーア戦争以降の出来事から彼が何かを学んだと思える兆候はほとんど無い。彼はその拡張段階におけるイギリス帝国主義の預言者であり(詩よりも、彼の際立った小説である消えた光から当時の雰囲気を知ることができる)、またイギリス軍の非公式な歴史家だった。かつての傭兵による軍隊は一九一四年になるとその形態を変化させ始めた。彼の自信、はつらつとした野卑な活力の全ては、ファシストやそれに近い者とは異なる短所からわき出していたのだ。
キップリングはその生涯の後半を不機嫌の中で過ごしたが、その理由が文学的むなしさよりも政治的失望にあったことを疑う余地はない。どうしたわけか歴史は計画通りに進まなかった。前代未聞の最高の勝利の後、イギリスは以前よりも劣った世界の大国となり、それを理解できるだけの十分な鋭敏さをキップリングは持っていた。彼が理想化していた美徳はその階級から消え失せ、若者は快楽かあるいは不平不満に走り、地図を赤く塗りつぶすという欲望は消滅してしまった。何が起きたのか彼には理解できなかったことだろう。なぜなら彼は帝国主義的拡張に内在する経済的力をまったく理解できていなかったからだ。特筆すべきは、帝国とはまず第一に営利事業なのだということに平均的な軍人や植民地の行政官と同様、キップリングが気づいていないように見えることだ。彼の理解では帝国主義とは一種の強制的福音伝道なのだった。非武装の「原住民」の群れにガトリング銃を突きつけ、その後に道路や鉄道、裁判所を含む「法」を制定する。こうした見方のために彼には帝国の存在をもたらしたのと同じ動機が最後にはその破壊をもたらして終わるということが予見できなかった。例を挙げれば、ゴム園のためにマレーのジャングルを一掃したのと同じ動機が、現在そのゴム園を無傷のまま日本人に手渡す原因となっているのだ。現代の全体主義者たちは自分が何をしているのかを理解しているが、十九世紀のイギリス人たちは自分が何をしているのかを理解していなかった。どちらの態度もそれぞれ長所はあるがキップリングには一方からもう一方へ進むことは決してできなかった。結局のところ彼は芸術家だったのだという事実を踏まえれば、彼の物の見方は「インドの小売り行商人」を見下す月給取りの役人のそれである。たいてい彼らは、その「行商人」こそが先行きを決めるのだということに気が付かないまま生涯を過ごす。
しかしながら自身を公的階級の人間だと考えていたために彼は「見識ある」人々がめったに、あるいはまったく持ち合わせていないものをひとつ持っていた。責任感である。中流階級の左派は彼の残忍さや野卑さと同じくらい彼のその資質を憎んでいる。高度に産業化された国の左派政党は全てその根底においては詐欺師である。なぜなら自ら進んで何かと戦いながらも、実のところそれを打ち倒そうとは願っていないからだ。彼らは国際主義者的目標を持ちながら、同時にその目標とは相容れない生活水準を維持しようと奮闘している。私たちは全員、アジアの苦力から収奪することによって生活を営んでいるが、私たちの中の「見識ある」者は全員、その苦力たちは解放されるべきだと主張している。しかし私たちの生活水準、すなわち私たちの「啓蒙主義」はその収奪が継続されることを要求しているのだ。人道主義者は決まって偽善者であり、キップリングがそれを理解していたことこそがおそらくは示唆に富むフレーズを作り上げる彼の力の核心的秘密なのだ。イギリスの視野の狭い平和主義者を表現するのに「眠っている間に自分を守ってくれる制服をあざ笑うこと眠っている間に自分を守ってくれる制服をあざ笑うこと:キップリングの詩「Tommy」の一節」というフレーズよりも短い言葉を考え出すのは難しいことではないだろうか。確かに彼は知識人と頑迷な保守派の間の関係が持つ経済的な側面を理解していなかった。地図が赤く塗りつぶされるのはまず第一に苦力から搾取するためであることが彼にはわからなかった。苦力の代わりに彼の目に映っていたのはインド人の役人である。しかしそうした地平に立ってさえ、彼の物事の働きに対する理解、誰が誰を守っているのかについての理解は非常に健全なものだったのだ。人間が高度に文明化できるのは他方で別の人間、必然的に文明の程度が低い者が存在して彼らを守り、食事を与えてくれる時だけであることを彼は明確に理解していた。
実際のところキップリングは自身が褒め称える行政官や軍人、技師にどれくらい自身を重ね合わせていたのだろうか? 時に思われているほど完全にそうしているわけではない。彼はまだ若かったころに非常に広い範囲を旅し、おおむね無教養な環境の中ですばらしい精神、そして繊細な者より活動的な者を好むようになかば反射的に導く自身の中の性向とともに育った。十九世紀のアングロ・インディアンは、彼の偶像と少しでも共鳴する者について言えば、多かれ少なかれ行動する人々だった。その行いは全て邪悪なものであったかもしれないが、彼らは地球の表面に変化を起こしたのだ(アジアの地図に目をやり、インドの鉄道網と周辺国のそれを見比べるとそれがよくわかる)。もし一般的なアングロ・インディアンの物の考え方が、例えばE・M・フォースターのようであれば彼らは何も成し遂げられなかっただろうし、一週間たりとも権力の座に留まることはできなかっただろう。安っぽく浅薄であるにも関わらず私たちの手にしている十九世紀のアングロ・インディアンについての文学的描写はキップリングのそれだけである。彼がそれを描き得たのは社交クラブや軍服姿の兵士の中にあっても口を閉じたままでいられるほど彼が無骨であったためだろう。しかし彼は自身が称賛した人々とはたいして似てはいなかった。複数の個人的な情報源から私が知ったところによるとキップリングの同時代人の多くは彼を好いても認めてもいなかった。インドについて何も知らないと彼らに言われ、確かにそれは真実だったし、また一方で彼らからすると彼はあまりに高尚すぎたのだ。インドにいる時には彼は「たちの悪い」人々と付き合う傾向があったし、自身が色黒だったために自分にアジア系の血筋が混じっているのではないかという誤った疑いを彼は持っていた。彼の発達過程のほとんどは彼がインドで生まれたことと学校を早い時期に去ったことに起因している。わずかでも背景が異なっていれば彼は優れた小説家や舞台歌曲の卓越した作家になれたことだろう。しかし実際のところ、彼が野卑な扇動家、セシル・ローズの宣伝係のようなものだったというのはどの程度、真実なのだろうか? それは真実ではあるが、彼がイエスマンやおべっか使いだったというのは間違いだ。初期はそうだったかも知れないが、それを過ぎた後、彼は決して世論に媚びようとはしなかった。エリオット氏は語っている。彼について言えるのは彼が評判の悪い意見を評判の良いやり方で表現したということだと。この「評判の悪い」を知識人に評判が悪いという意味だと考えると発言の意味は狭まってしまうが、キップリングの「メッセージ」は大衆が望まず、また間違いなく受け入れないものであったことは事実である。九十年代時点では人々の大部分は反軍国主義で、帝国に飽き飽きし、愛国的であるのは無意識下でのみのことだった。キップリングの表立ったファンは「軍で働く」中流階級、ブラックウッズ誌を読む人々であり、それは今と変わらない。今世紀初頭の愚かな数年の間、ついに自分たちの陣営に属した詩人と呼ぶことのできる人物を発見した頑迷で保守的な人々はキップリングを台座にすえつけ、「もし」のような比較的教訓的な詩のいくつかにはほとんど聖書のごとき地位が与えられた。しかし彼ら保守派がこれまで一度でも聖書を読む時以上の注意を払って彼の作品を読んだことがあるかは疑問である。彼の言っていることの多くはおそらく彼らには受け入れることのできないものだ。イングランドを内部から批判していた者で、この心底からの愛国者よりもずっと厳しいことを言っていた者はわずかしかいない。彼が非難していたのは概してイギリスの労働階級だったが、常にそうであったわけではない。「クリケットの打席に立つフランネルを着た愚か者とフットボールのゴールを守る泥だらけののろま」というフレーズは現代に対しても矢のように突き刺さり、それはイートン校・ハロウ校の対抗戦とフットボール優勝杯争奪決勝戦に等しく狙いを定めたものなのだ。ボーア戦争について彼が書いた詩のいくつかからは、その主題を思えば奇妙なほど現代的な印象を受ける。一九〇二年頃に書かれたに違いない「ステレンブーシュステレンブーシュ:南アフリカ共和国西ケープ州の町の名前。ボーア戦争の際に基地として使われた。」は、その題材に関して言えば知識階層の歩兵隊将校全員が一九一八年、あるいは今でも口にすることをまとめ上げたものに他ならない。
イングランドと帝国に対するキップリングのロマン主義的考えは、当時それらにつきまとっていた階級的偏見無しに彼がそれを奉じていたとしても何らおかしくないものだった。彼の最高にして最も代表的な作品である兵士についての詩、特に兵舎のバラッドを調べると、それらを他の何よりも損なっているのはそこに潜在するパトロン的雰囲気であることに気がつく。キップリングは陸軍将校、特に下級将校を馬鹿馬鹿しいほど理想化し、一方で兵卒は愛嬌があり空想的ではあるが必ず滑稽に描かれている。決まってある種の定型化された下町訛りで話すよう描かれているのだ。全てがそうであるというわけではないがHの音と末尾の「g's」は注意い深く取り除かれている。その結果としてしばしば起きるのは教区の親睦会で起きる滑稽な反応に似た当惑である。そしてこれはキップリングの詩を読んでそれを下町訛りから標準英語に翻訳するとそれだけで軽薄さとわざとらしさが減り、わかりやすくなることが多いという奇妙な事実を説明する。まさに叙情的な質を左右することが多い反復部分にはとりわけこれが当てはまる。二つの例を引こう(ひとつは葬列について、もうひとつは結婚についてのものだ)。
さあパイプの灰を打ち捨て、ついて来い!
気の抜けたビールを飲み干して、ついて来い!
ああ、あの大きな太鼓の音に耳を傾けよ
ついて来い……ついて来い、ふるさとへ!
もうひとつはこうだ。
軍曹の結婚式へ喜びの声を……もうひとつ喜びの声を!
ランドー馬車を引く灰色の軍馬
そしてならず者が娼婦と結婚する!
ここで私はHの文字などを補っている。キップリングもずっとよくわかっているはずだ。これらの連のひとつ目の締めの二行が実に美しいことも、労働階級の人間のアクセントをからかう衝動に自らが負けてしまっていることも彼にはわかっているはずなのだ。古くからあるバラッドでは貴族と貧農は同じ言葉を話す。これは階級的態度が歪んでいくことを見下していたキップリングには不可能なことであり、詩的正義の一部によって彼の最高の数行のひとつは損なわれた……「follow me home」よりもずっと醜い「follow me 'ome」によって損なわれたのだ。しかし、たとえ音の調べに何の違いも生まれなかったとしても彼の舞台がかった下町訛りの軽薄さは癇に障るものだ。とは言え彼は印刷されたページで読まれるより声に出して引用される方がずっと多く、ほとんどの人々は彼を引用する時には無意識に必要な調整を加えている。
九〇年代であれ現在であれ、兵舎のバラッドを読んで自分を代弁してくれる作家がいたと感じる兵卒を想像できるだろうか? 実に難しいことだ。詩集を読むだけの能力がある兵士であれば誰でもすぐに他の場所と同様、軍隊の中で繰り広げられている階級闘争をキップリングがほとんど意識していないことに気がつくだろう。彼は兵士を滑稽なものと考えているだけでなく、兵士は愛国的、封建的で、上官を喜んで信奉し、女王の兵士であることを誇りにしていると考えているのだ。もちろんそれは部分的には真実である。そうでなければ戦うことなどできないだろう。しかし「汝のために何をなし得よう、イングランド、我がイングランド?汝のために何を成し得よう、イングランド、我がイングランド?:ウィリアム・アーネスト・ヘンレイの詩「イングランド、我がイングランド」の一節」という問いは本質的には中流階級のものなのだ。労働階級の人間であればほとんど誰であってもすぐさま「イングランドは私のために何をしてくれるのか?」と続けることだろう。これに関するキップリングの理解について言えば、彼はたんに「下方階級の強烈な利己主義」(彼自身の言葉だ)と考えただけだ。イギリス人でなく「忠実な」インド人について書く時には、「おおせのままに、閣下」式のモチーフを持ち出し、ときおりそれはうんざりするほど長くなる。しかしここでもまた、彼が当時や現在の「リベラル」のほとんどよりもずっと熱心に兵卒に関心を寄せ、公平な扱いを受けられるように心を砕いていたことは真実である。兵士によって収入を守られている人々から兵士が顧みられず、ひどい低賃金を押し付けられ、偽善的に侮蔑されていることを彼は理解していた。「私が気がついたのは」。死後に出版された回顧録で彼は語っている。「兵卒の生活のむき出しの恐怖、そして彼が耐えている不必要な苦痛である」。彼は戦争を美化したとして非難されている。確かに彼はそれをおこなったのだろうが、それはよくあるやり方とは違ってまるで戦争がフットボールの試合か何かのように装うことによってだった。戦争詩を書く能力のある人々のほとんどと同様、キップリングには従軍経験がまったく無かったが戦争に対する彼の見方には現実味があった。銃弾の痛み、銃声の下では誰もがおびえること、これが何のための戦争なのか、あるいは自分のいる戦場の片隅を除けば何が進行しつつあるのかを普通の兵士がまったく理解していないこと、他の軍隊と同様にイギリスの軍隊がよく逃げ出すということを彼は知っていた。
背後にナイフの気配を感じたが、仲間に顔を向けることもせず、
進むべき先もわからなかった、立ち止まって先を見据えることもしなかったから
それもひとりの貧者が走りながら命乞いの金切り声を上げるまでのこと
この声は聞き覚えがあるぞと私は思った……それは私だったのだ!
これを現代風に書き換えれば一九二〇年代に書かれた戦争の実態を暴露する作品のひとつに変わることだろう。さらにひとつ挙げよう。
今やひどく醜悪な弾丸が砂ぼこりを突き抜けて襲いかかる
それに向き合おうという者はひとりもいないが、全ての貧者はそうしなければならぬ
まるで足枷をつけられた者のように、気乗りしない調子で進むのだ
ぎこちなくのろのろと、隊を作って歩みを進める
これを以下のようなもの以下のようなもの:アルフレッド・テニスンの詩「軽騎兵の突撃」の一節と比較してみて欲しい。
軽騎兵、前進!
うろたえた者はいただろうか?
否! 兵士はわかっていた
誰かが失態を演じたのだということを
どちらかと言えばキップリングは恐怖を誇張しすぎていると言える。なにしろ彼の青年時代における戦争は現在の基準から見ればまったく戦争とも呼べないようなものなのだ。おそらくこれは神経的緊張、残酷さへの飢えによるものだろう。しかし少なくとも彼は、手に負えない目標への突撃を命じられた人間がうろたえることを知っていたし、一日あたり四ペンスの恩給が気前のいいものではないことも知っていた。
キップリングが私たちに残した十九世紀後半の長期軍務の雇兵軍隊の描写はどれくらい正確なものなのだろうか? 十九世紀のアングロ・インディアンについてキップリングが書いたものに関して言っておかなければならないのは、それが最良というだけでなく、私たちが手にしているほとんど唯一の文学的描写であるということだ。彼は膨大な量の物事についておおやけに語った。それらはもし彼がそうしなければ口伝による言い伝えか、読みづらい軍史から収集する他なかったものだ。おそらく彼の描く軍隊生活は実際のそれよりも充実し、折り目正しいものに思えることだろう。これはイギリスに住む中流階級の人物であれば誰しもそのギャップに気づくだけの十分な知識を持っているためだ。いずれにせよ、エドマンド・ウィルソン氏が出版した、あるいはこれから出版しようとしているキップリングに関するエッセイ[以下注記]を読みながら、私たちにとってはうんざりするほどおなじみだがアメリカ人にとってはほとんど理解に不能に思える物事の多さに私は衝撃を受けた。しかしキップリングの初期の作品の多くからは鮮明で、大きな誤解の余地のない、古風な機関銃以前の時代の軍隊の様子が浮かび上がるように思われるのだ……ジブラルタルやラクナウのうだるように暑い兵舎、イギリス軍歩兵、パイプ粘土で漂白されたベルトとピルボックス帽、ビール、けんか、鞭打ち、絞首刑や磔刑、集合ラッパ、オート麦と馬の小便の臭い、一フィートほども口ひげを伸ばした怒鳴り散らす軍曹、血塗られた小競り合い、必ず起きる管理上の不手際、満員の兵員輸送船、コレラの蔓延する野営地、「現地」妻、救貧院での最終的な死。下品で野卑な風景はまるで愛国的な大衆演劇場とゾラゾラ:フランスの小説家であるエミール・ゾラを指すのむごたらしい一節が混じり合ったかのようである。しかし将来の世代はそこから長期にわたる志願制軍隊がどのようなものだったかについての何らかの考えを得ることができるだろう。またそれと同じ水準で、自動車や冷蔵庫など耳にすることもない当時のイギリス領インドについて何事かを学ぶことができるはずだ。例えばジョージ・ムアやギッシング、トーマス・ハーディがキップリングと同じ条件にあったなら、私たちはこうした題材に関するもっと優れた書籍を手にすることができただろうと想像するのは誤りだ。それは決して起きようのない出来事である。戦争と平和、あるいはトルストイのもっとマイナーな軍隊生活の物語に類した書籍を十九世紀のイングランドが生み出すことはあり得ない。それは必要な才能を持つ人物がいなかったためではなく、こうした書籍を書くための十分な感受性を持つ者はそのための適切な接点を持とうとはしないであろうためだ。トルストイは巨大な軍事帝国に住んでいて、そこでは一家の若い男であればほとんど誰でも数年を軍隊で過ごすのが自然なことだと思われていた。一方で大英帝国は当時も今も、大陸の観測筋が見たらほとんど信じがたいほどに非武装的である。文明化された人間は文明の中心から容易に離れはしないし、ほとんどの言語では植民地文学と呼ばれるであろうものがまったく不足している。ヤシの木と聖堂の鐘の音を背景に兵卒オーテリスとホークスビー夫人がポーズをとる、キップリングのけばけばしい芝居がかった場面を生み出す条件とキップリング自身が半分だけ文明化されているというもうひとつの必要な条件は極めて成立しづらい組み合わせだったのだ。
[注記:エッセイ集である傷と弓に収録されて出版された(原著者脚注、一九四五年)]
キップリングはこの言語に新たな言い回しを付け加えた、現代における唯一の英語作家である。私たちが受け継ぎ、その起源を思い出すこともなく使う言い回しは、必ずしも称賛を集める作家によって作り出されたものではない。例えば奇妙にもナチの放送局がロシア兵を「ロボット」と呼ぶのを耳にすることがある。無意識に拝借しているその言葉は、もしナチが彼を手中に収めたら間違いなく殺すであろうチェコの民主主義者によって生み出されたものだ。ここにキップリングによって作り出された言い回しを半ダースほど挙げておこう。タブロイド紙の社説で引用されていたり、サロン・バーで彼の名前などほとんど聞いたこともない人々の口から耳にしたりする言い回しだ。それら全てが共通して持つある特徴が見て取れるだろう。
東は東、西は西
白人の責務
イングランドしか知らない者にイングランドの何がわかるというのか?
種のメスはオスよりもずっと恐ろしいものだ
スエズの東のどこか
デーンゲルトを払う
他にも様々なものがあり、中には長い年月を経てその文脈が忘れ去られたものもある。例えば「その口でクルーガーを殺す」という言い回しはつい最近までよく使われていた。またドイツ人を「Huns(ドイツ野郎)」という言葉を使って最初に呼んだのはキップリングだったのではないだろうか。いずれにせよ、彼がその言葉を使い出したのと一九一四年のあの戦火が巻き起こったのは同時期のことだった。しかし私が先に挙げた言い回しで共通しているのは、それらの言い回し全てが半ば嘲笑と共に発せられる言葉(「だって私は五月の女王になるから、母さん、五月の女王にだって私は五月の女王になるから、母さん、五月の女王に:アルフレッド・テニスンの詩「五月の女王」の一節」のようなものだ)でありながら、しかし遅かれ早かれ使ってしまうものであるということなのだ。例えばキップリングへの侮辱でニュー・ステーツマン誌を凌駕できるものは無いだろうが、ミュンヘン会談の時期にニュー・ステーツマン誌は何度、デーンゲルトを払うという言い回しを引用しただろうか?[以下注記]実のところ、その雑学知識と実に安っぽい視覚的情景を数語(「ヤシとマツ」―「スエズの東」―「マンダレーへの道」)に詰め込む彼の才能を別にすれば、キップリングが語るのはもっぱら差し迫った関心事についてなのだ。こうした観点に立つと、思慮と慎みある人々が概して彼と柵を挟んだ反対側に自身を見出すことはたいした問題ではないことがわかる。「白人の責務」は、たとえもしその言葉は「黒人の責務」と変えられるべきだと感じようとも即座に現実の問題を想起させる。「島人」でほのめかされる政治的態度には骨の髄まで反対するだろうが、それを軽薄な態度と呼ぶことはできない。思考の上ではキップリングは野卑であるとともに普遍的なものを扱っているのだ。これによって詩人、あるいは韻文作家としての彼の特別な地位についての疑問が提起される。
[注記:ミドルトン・マリー氏は、彼の最近の作品であるアダムとイブの最初のページで有名な数行を引用している。
部族の伝承の歌を作り上げるには
九つと六十のやり方があり
そのどのひとつをとっても正しいものなのだ。
彼はこれらの数行をサッカレーのものであるとしている。これはおそらく「フロイト的誤り」として知られているものだ。文明化された人物は好んでキップリングを引用しようなどとはしない……つまり、自らに代わってその考えを表現してくれるのがキップリングであると感じたくはないのだ。(原著者脚注、一九四五年)]
エリオット氏はキップリングの韻律的作品を「詩」ではなく「韻文」と表現している。ただしそれは「優れた韻文」であると彼は付け加え、さらに、その作品の中に「韻文なのか詩なのかわからない」ものがある場合にのみ、その作家は「優れた韻文作家」と表現されると言って条件を付け加えている。明らかにキップリングはときおり詩を書く韻文作家であるが、書くのが詩である場合にもそれはエリオット氏がそれらの詩の名前を挙げないほど悲惨なものだった。厄介なのはキップリングの作品に対する美的判断は決まって論議を呼ぶように思われることで、エリオット氏は過剰に防御的になっているために率直な物言いをできなくなっている。彼が口に出さず、私がキップリングについて何か議論するのであればまず始めに言わなくてはならないと考えているのはキップリングの韻文が恐ろしく野卑だということだ。まるで三流大衆演劇場の演者が顔に紫のスポットライトを浴びながら「ウー・ファン・フーの豚のしっぽウー・ファン・フーの豚のしっぽ:二十世紀初頭の流行歌である「リー・ファン・フーの豚のしっぽ(The Pigtail of Li-Fang-Fu)」 を指しているものと思われる」を朗唱するのを見ている時と同じような気持ちになる。しかしそれでもなお、そこには詩が何を意味するのかを知る人々に喜びを与えることができるだけのものが多く含まれているのだ。彼の最悪の、そしてまた最も生き生きとした「ガンガディン」や「ダニー・ディーバー」のような詩でのキップリングには恥ずべきと言っていいほどの喜びがあり、それはまるで中年に差し掛かった人々の一部が密かに持ち歩いている安菓子の味のようだ。しかし彼の最高の一節からさえも、欺瞞的な何かによって誘惑されているという感覚を受ける。そして現にそれは紛れもない誘惑なのだ。詩に関心のある者で、次のような一節からは何ら喜びを得られないと言えるのは高慢で嘘つきな人間だけだろう。
風がヤシの木の間を吹き、寺の鐘が告げる
「戻り来たれ、イギリスの兵よ、戻り来たれ、マンダレーへ!」
しかしまたこれらの一節は「フェリクス・ランダルフェリクス・ランダル:ジェラード・マンリ・ホプキンスの詩」や「つららが壁にかかる時つららが壁にかかる時:ウィリアム・シェイクスピアの詩」といった詩と同じ意味においては詩ではない。おそらくキップリングを満足のいくように分類するには「韻文」や「詩」という言葉を使って評価を下すよりも、彼をたんに優れた俗悪詩人と表現した方がよいのだろう。彼は、ハリエット・ビーチャー・ストウハリエット・ビーチャー・ストウ:「アンクル・トムの小屋」の著者が小説家であるのと同じ意味において詩人なのである。そしてこうした種類の作品が存在し続けていること、何世代にも渡って野卑であると受け取られ、それでもなお読み続けられることは私たちの住む時代について何事かを教えているのだ。
英語には優れた俗悪詩が大量にある。その全てが一七九〇年以降のものであると言っていいだろう。優れた俗悪詩の例は……意図して様々なものを挙げるが……「ため息の橋」、「全ての世界が若く、向こう見ずだった頃」、「軽騎兵の突撃」、ブレット・ハートの「野営地のディケンズ」、「ジョン・ムーア卿の埋葬」、「ジェニーとの口づけ」、「ラヴェルストンのキース」、「カザビアンカ」といったものだ。これらはどれも嫌に感傷的だが、また……これらの一部はそうでないかも知れないが……こうした種類の詩はそれらのどこが悪いのかを明確に理解できる人々に対しても真の喜びを与えることができるのだ。優れた俗悪詩が普通は広く知られすぎていてそれらが普通は再版する価値がないという重要な事実が無ければ、優れた俗悪詩でかなりの長編の選集を編むことができるだろう。
現代のような時代において「優れた」詩は偽りのない人気を得られるものだと装うのは無益なことだ。得られるのはごくわずかな人々への個人崇拝、この芸術への最低限の寛容に過ぎない。おそらくこの意見にはある程度のただし書きが必要だろう。真の詩は時に人々の多くに受け入れられることもあるが、それはその詩が自らを別の何かに偽装している場合だけなのだ。この例を目にすることができるのがイングランドにいまだ残る民族詩、例えばわらべ歌や記憶のための語呂合わせであり、また兵士たちの作る、集合合図などで使われる言葉を含んだ歌である。しかし一般的に言えば私たちの時代は文明化されていて、そこでは「詩」という言葉そのものが引き起こすのは敵意ある忍び笑い、良くて「神」という言葉を聞いた時に人々の多くが感じる悪寒のようなものなのだ。もしコンサーティナを演奏するのが上手ければ、近くの酒場に行って耳の肥えた聴衆を五分で得ることができるだろう。しかし、もしそこで例えばシェイクスピアのソネットを朗読して聞かせると言ったら、その同じ聴衆はどのような態度を取るだろうか? とは言え、前もって適切な雰囲気を作り上げていれば優れた俗悪詩は最も見込みのない聴衆であっても理解され得る。数ヶ月前、チャーチルは演説放送のひとつでクラフクラフ:アーサー・ヒュー・クラフ。十九世紀のイギリスの詩人。の詩「企て」を引用して大きな効果を生み出した。まず間違いなく詩に関心が無いであろう人々に混じって私はこの演説を聞いたが、韻文への移り変わりが彼らに感銘を与え、困惑を生み出してはいないことを確信した。しかしチャーチルであっても、それよりもずっと品のいいものを引用していたなら困惑無しに済ませることはできなかっただろう。
人気のある韻文作家という意味で言えばキップリングはおそらく今も人気がある。彼の生きた時代において彼の詩は一般読者の垣根を超えていた。学校での表彰式、ボーイスカウトの唱歌、革装の私家版、焼き絵やカレンダーを超え、大衆演劇場の広大な世界へさえ流れ込んでいた。それにも関わらず、エリオット氏は編集をおこなう間その価値について考えあぐね、それ故に他の者たちが共有しながらも必ずしも誠実に口にすることのない思いを告白している。優れた俗悪詩のような物が存在し得るという事実は知識人と一般人の間に感情的に重なり合う部分があることを示しているのだ。知識人は一般人とは異なるが、それは人格の特定の部分にのみ限られたことで、しかも常に異なっているというわけでさえない。しかし優れた俗悪詩の特徴とはどのようなものだろうか? 優れた俗悪詩は明白なものの優美な記念碑なのだ。そこにはほとんど全ての人間が共有することのできる感情のいくつかが記憶に残る形で……韻文は他の何物にも勝る記憶装置だ……刻まれている。「全ての世界が若く、向こう見ずだった頃」といった詩の長所は、それが感傷的なものであったとしても、そこで表現された考えに遅かれ早かれ自分自身で思い当たるという意味でその感傷が「正しい」感傷であるということだ。そしてもしその詩を偶然にも知っていた場合には頭の中にそれがよみがえり、以前よりもずっとすばらしいものに思えるのだ。こうした詩は一種の韻を踏んだことわざであり、明確に人気のある詩は普通は格言的、教訓的ものであるのが実態である。キップリングから例をひとつ挙げよう。
手綱にしがみつく腕
ブーツのかかとから拍車が滑り落ち
柔らかな声が叫ぶ「戻って来て!」
赤い唇が鞘に納められた剣を曇らせ
地獄へと下るか、玉座へと上がるか
並ぶ者の無い速さでひとり彼は進む
活力ある表現による通俗的な感情がここにはある。実際にこうした経験をすることは無いだろうが、多かれ少なかれ誰しもが考える思いである。遅かれ早かれ、並ぶ者の無い速さでひとり彼は進むと感じることがあるだろうが、その時にはその感情はあらかじめ用意され、まさにそのままの形で待ち受けているのだ。そしてひとたびこの一節を耳にすれば、それを思い出すことになるだろう。
優れた俗悪詩としてのキップリングの持つ力の理由のひとつはすでに示してみせた通りだ……彼の責任感が彼に世界観を持つことを可能にさせた。たとえ偶然にもそれが誤ったものであったにせよである。キップリングはどの政党とも直接的なつながりを持ってはいなかったが、彼は保守主義者であり、それは現在では存在しないようなあり方でのものだった。現在、自身を保守主義者と呼ぶ者たちはリベラルか、ファシストか、ファシストの共犯者である。彼は自らを野党ではなく統治権力と一致させていた。ひとりの才能ある作家として見た時、私たちにはこれが奇妙で不愉快なことのように思われるが、そこにはキップリングに現実を確実に把握させる力を与えるという大きな長所もあった。統治権力は「これこれの状況において、どのように行動するのか?」という問いに絶えず直面させられる一方で、野党は責任を負うことも何らかの現実的決断をおこなうことも迫られない。イングランドでそうであるように交付金を給付された万年野党である場合には、それによってその思想の質は劣化していく。さらに言えば実際の出来事によって裏打ちされがちな、人生に対する悲観的で反動的な考えから出発する者は誰であってもユートピアが決して到来しないことや「手習い帳の見出しにいる神々」を理由に、キップリング自身がそうであったように決まって元いたところへと舞い戻るのだ。金銭的にはそうでないとしても感情的にはキップリングはイギリスの支配階級に自身を売り渡した。このことは彼の政治判断を歪めた。イギリスの支配階級は彼が想像したようなものではなかったからだ。それによって彼は愚かさと高慢の奈落へと導かれたが、少なくとも行動と責任はどのようなものであるべきか想像しようと試みたことで彼は相応の長所を育んだ。彼が機知に富んでもいなく大胆でもなかったこと、ブルジョアの鼻をあかそうと望まなかったことは彼にとってはすばらしいことだった。彼は大部分において陳腐に振る舞い、私たちの住む世界が陳腐であるために彼の語ったことのほとんどはそのまま留まり続けている。そして同時代の「進歩的」な言葉、ワイルドワイルド:イギリスの詩人、劇作家、小説家であるオスカー・ワイルドを指すの警句や人と超人人と超人:バーナード・ショーによる戯曲の巻末にあるクラッカー・モットーの一覧よりも彼の最悪の愚行の方が浅薄なところや癇に障るところが少なく思えさえするのだ。