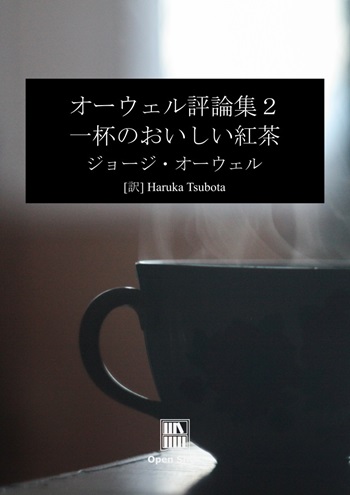スポーツ精神
ようやくディナモ・フットボールチームディナモ・フットボールチーム:1945年にイギリスを訪問したサッカーチームのFCディナモ・モスクワを指すの短い滞在が終わりを迎え、多くの思慮ある人々がディナモ到着前に密かにささやいていたことをおおやけに語ることができるようになった。それはスポーツは無尽蔵にわき上がる敵意の源であり、もし今回のような滞在がイギリスとソビエトの関係になんらかの影響を与えるとしたら、関係を以前より悪くするくらいのものだろうということだ。
おこなわれた四試合のうちの少なくとも二試合がひどく険悪なものになったという事実は新聞でさえ隠しきることはできなかった。その場にいた人間に私が聞いたところではアーセナルアーセナル:ロンドン北部を拠点にするサッカーチームのアーセナルFCを指すとの試合ではイギリス人選手とロシア人選手が殴り合いになり、観客から審判にブーイングが飛んだという。また別の者によるとグラスゴーグラスゴー:イギリスのスコットランド南西の都市。セルティックFC、レンジャーズFCといったサッカーチームが拠点にしている。の試合は試合開始からまさになんでもありの乱闘状態だったそうだ。その上、ナショナリスティックな現代に典型的な論争である。内容はアーセナルのチームメンバーの構成についてだ。あれはロシア人たちが主張するように真のイギリス代表チームなのだろうか? それともイギリス人たちが主張するようにたんなるリーグチームなのだろうか? そしてディナモが唐突にツアーを終えたのはイギリス代表チームとの試合を回避するためだったのだろうか? 常のごとく、これらの疑問には誰もが自身の政治的な傾向に従って答えをだす。しかし例外もいる。フットボールが引き起こす暗い情熱による興味を持って私が目にしたところによれば、ロシアびいきのニュース・クロニクルのスポーツ記者は反ロシアの戦列に加わり、アーセナルはイギリス代表チームではなかったという立場を崩さなかった。今回の論争が歴史の本の脚注に何年にもわたってこだまし続けるだろうことは疑いない。一方で、もしなんらかの結果があったとすればだが、このディナモのツアーの結果は両陣営に生々しい敵対意識を作り出すことだろう。
しかしそれも当然のことではないだろうか? スポーツは国々の間に友好を築く、もし世界の民衆がフットボールやクリケットで互いに顔をあわせることができれば戦場で顔をつき合わせようなどという気持ちは持たないだろう、と人々が言うのを聞くたびに私はいつも驚かされる。国際的なスポーツ競技会が憎悪の発端となる具体的な例(例えば一九三六年のオリンピック大会)を知らないとしても、一般的な原理からそれは推測できるはずなのだ。
現在おこなわれているスポーツのほとんど全ては競争的なものだ。勝利を得るためにおこなわれ、もし勝利のために最大限の努力をしないのであれば試合はほとんど意味のないものになる。どちらのチームにつくか選べて郷土愛の感情に巻き込まれることのない、村の草原でおこなわれるようなものであれば純粋な楽しみと運動のためにプレーすることも可能だろう。しかしそれが威信をかけたものになり、もし負ければ自分とより大きな構成単位の面目が失われると感じるやいなやもっとも野蛮な闘争本能が呼び覚まされるのだ。学校対抗のフットボールの試合をしたことがあるものであれば誰でも知っていることだ。国際的なものともなれば率直に言ってスポーツは戦争の模倣になる。しかし重要なのは選手たちの振る舞いではなく、むしろ観客の態度、そして観客の背後にいる国家の態度だ。彼らはこの馬鹿げた競争に怒りを爆発させ……短期間とは言え……走ったり、跳ねたり、ボールを蹴ったりすることが国家の徳を試すものだと真剣に信じる。
力強さよりも優雅さが要求されるクリケットのようなのんびりしたスポーツでさえ、大きな敵意を引き起こすことがある。私たちはそれをボディーライン戦術ボディーライン戦術:クリケットの戦術の一つで打者に向かってボールを投げる。イギリスチームが生み出した。や一九二一年にイギリスを訪れたオーストラリアのチームのひどい戦術に対する論争で目にしてきた。皆が傷を負い、外国人から見ればフェアでないように思える独自のプレースタイルがどの国にもあるフットボールはもっとずっとひどい。最悪なのはボクシングだ。白人と有色人種のボクサーがそれぞれの人種が入り混じった観客の前でおこなう試合は世界でもっとも恐ろしい光景の一つだ。しかしそうでなくともボクシングの観客は下品で、とりわけ女性の振る舞いは軍隊であれば彼女たちが試合を見ることを許可しないほどだと私は思う。少なくとも、二、三年前にホーム・ガードホーム・ガード:第二次世界大戦中にイギリスで編成された民兵組織。オーウェルも参加していた。と常備軍の間でおこなわれたボクシングのトーナメントではホールの門衛に配置された私には女性を入れるなという命令が下されていた。
イギリスでもスポーツへの熱中は十分ひどいものだが、スポーツとナショナリズムが最近になって発達した若い国々ではさらにすさまじい情熱が呼び覚まされている。インドやビルマといった国々では、フットボールの試合がおこなわれる際に警察は強力な非常線を張って群衆がフィールドに入り込むのを防ぐ必要がある。ビルマでのことだが、片方の側のサポーターたちが警察を突破して決定的な瞬間に相手側のゴールキーパーを妨害したのを私は目にしたことがある。十五年ほど前にスペインで開かれた最初のフットボールの大きな試合では制御不能な暴動が起きた。強い敵対感情がわき上がるやいなやルールに従ってゲームをプレーするという考えは決まって消え失せるのだ。人々は片方の側が栄誉を得て、もう一方が屈辱にまみれるのを見たいと欲し、不正や群衆の乱入によって得られた勝利は無意味だということを忘れてしまう。観客が物理的に手出ししない時であっても彼らは味方側に声援を送り、ブーイングや侮蔑の言葉で相手側の選手を「威嚇」することでゲームに影響を与えようとする。真剣なスポーツはフェアプレーとは無縁だ。それが密接な関係を持つのは憎しみ、妬み、傲慢、あらゆるルールに対する軽視、そして暴力を目にするというサディスティックな喜びである。言い換えればそれは戦争から銃撃を引き算したものなのだ。
フットボール場での公平で健康的な競争だの、国々を結びつけるためのオリンピック大会の重要な役割だのといったごたくを並べる代わりに現代のスポーツ崇拝がどのように、そしてなぜ発生するのかを調べるほうがよほど有用だ。現在、私たちがおこなうスポーツのほとんどは古代にその起源を持つがローマ時代から十九世紀までの間、スポーツがこれほど真剣に取り上げられることはなかったように思われる。イギリスのパブリックスクールにおいてさえ前世紀の後半になるまでスポーツ崇拝が見られることはなかった。近代的なパブリックスクールの創設者として一般に知られるアーノルド博士はスポーツをたんなる時間の浪費と考えていた。その後、主にイギリスと合衆国でスポーツは非常に大きな経済活動へと仕立てあげられ、膨大な群衆を惹きつけて野蛮な情熱を喚起することができるようになり、その影響は国から国へと広がっていった。もっとも広まったのはもっとも暴力的で闘争的なスポーツであるフットボールとボクシングだった。これらすべてがナショナリズム……つまり巨大な権力単位と自身を同一視し、全ての物事を威信を競い合うという観点からのみ見るという狂った現代の傾向の高まりと密接に関係していることは疑いようもない。また組織的なスポーツ活動は都市部のコミュニティーで盛んになることが多い。そこでは平均的な人間は運動不足な生活か少なくとも閉じこもりがちな生活を送り、創造的な仕事をおこなう機会は限られている。田舎では少年や若い男性は大量の持て余したエネルギーを散歩や水泳、雪合戦や木登りや乗馬といったさまざまなスポーツで解消する。そこには魚釣りや闘鶏やフェレットを使ったねずみ狩りといった動物に対する残酷な行為も含まれる。大都市では体力やサディスティックな衝動のはけ口を求めれば集団による活動でうっぷんを晴らすほかない。スポーツが真剣な関心事なのはロンドンやニューヨークでのことであり、ローマやビザンチウムでのことだった。中世でもスポーツはおこなわれたし肉体的な荒々しさは今よりもひどかったことだろう。しかしそれが政治と交わることも集団憎悪の原因になることもなかった。
この瞬間に世界に存在する膨大な量の敵意の積み立てをもしさらに増やしたいと思えばフットボールの試合に勝るものはないだろう。ユダヤ人とアラブ人、ドイツ人とチェコ人、インド人とイギリス人、ロシア人とポーランド人、イタリア人とユーゴスラビア人の間で、それぞれの人種が入り混じった十万の観客が見守るなかおこなわれる試合だ。もちろん国家間の敵対状態の主な原因の一つがスポーツであると言いたいわけではない。大規模におこなわれるスポーツそれ自体は私が考えるところではナショナリズムを生み出す原因が引き起こすもうひとつの結果に過ぎない。だが他のライバルチームと戦わせるために国内王者の称号を与えた十一人の男からなるチームを送り出し、それがどちらであろうが敗れた国はあらゆる点で「面目を失う」と感じることを許せば事態はよりいっそうひどくなる。
だからこそディナモの滞在が終わった後、イギリス代表チームをソ連に派遣するべきではないと私は思う。もしどうしてもそうしなければならないのであれば間違いなく負ける、イギリス全体を代表しているとはとうてい呼べない二線級のチームを派遣するべきだ。すでにトラブルの種は十分すぎるほどある。怒りに駆られた観客の叫び声の中で若い男たちに向こうずねで互いを蹴り合わせてそれをさらに増やす必要など無いのだ。