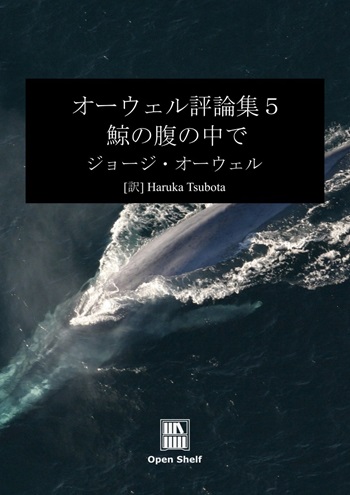W・B・イェイツ
マルクス主義者の批評でうまくいかないことのひとつは「傾向」と文学スタイルの間のつながりを明らかにすることである。作品の主題とイメージは社会学的用語で説明できるが質感に対してはそれができないように思えるのだ。しかしそうしたつながりは必ず存在するはずである。例えば、なぜそれがわかるのかを言葉にすることは容易でないにせよ、社会主義者がチェスタートンやあるいはバーナード・ショーのようなトーリー的、帝国主義者的な文章を書かないであろうことはわかる。イェイツの場合、気まぐれで苦悩的とさえ言えるその文体とその極めて悪意ある人生に対する見方の間になんらかのつながりがあることは間違いない。メノン氏はもっぱらイェイツの作品に内在する難解な哲学に考えを巡らせているが、この興味深い書籍全体に散らばる疑問はイェイツの書き方がどれほど作為的なものであるかを思い出させてくれる。一般にこの作為性はアイルランド的なものとして受け取られている。あるいは短い語を使うことを理由にイェイツに簡潔さの称号が与えられることさえある。しかし実のところ彼の詩で古語や気取った言い回しが存在しない行が六行も続くことはめったにない。手近な例を挙げてみよう。
老いた者の狂乱を私に許したまえ
作り直さなければならぬのは私自身
タイモンやリアへ私がいたるまで
あるいは、かのウィリアム・ブレイク
壁を打つ者
真実がその呼びかけに従うまで
不必要な「かの」が気取った感じを持ち込んでいるが、これと同じ傾向はイェイツの最も優れた節回しを除くあらゆるところに見られる。「古典趣味」の疑念を抱かずにいられることはめったにない。そこにあるのはあの九十年代、象牙の塔と「色あせた緑の子牛皮の表紙色あせた緑の子牛皮の表紙:ユリシーズの第十四章からの引用」、そしてまたラッカムラッカム:アーサー・ラッカム。イギリスの挿絵画家で、特にメルヘンやファンタジー作品の挿絵で知られる。の挿絵やリバティ・アート・ファブリックスリバティ・アート・ファブリックス:ロンドンにある美術工芸品の販売店、ピーターパンのネバーランドと結びついた何かだ。そして「楽しき街区楽しき街区:イェイツによる詩。「The Happy Townland」。」はそれのより魅力的な例に過ぎないのだ。これはさして重要な問題ではない。なぜなら全体的に見てイェイツはそれを使ってうまく急場をしのいでいるし、もし彼の歪んだ後味がしばしば癇に障るものであっても、同時にそれはフレーズを生み出し(「寒々とした、根無しの年月」、「サバの群れる海」)そのフレーズは部屋の向こうの少女の顔のように唐突に人を圧倒するのだ。詩人は詩的な言葉を使わないというルールは彼には当てはまらない。
幾世紀を過ごしただろうか
腰を下ろした魂よ
推量の労苦の中
ワシやモグラの域を超えて
音も光も、
アルキメデスの思慮も届かぬ先へ
到達しえるか
その魅力へ?
ここでも彼は「魅力」のような曖昧でおおざっぱな言葉にひるまないが、結局のところそれによってこのすばらしい一節がひどく損なわれているわけではない。しかしまさにこれと同じ傾向が、疑いなく意図的なものである、ある種の不協和とともに彼の警句と論争的詩の効果を弱めている。例えば(記憶から引くが)西の国の伊達男西の国の伊達男:アイルランドの作家ジョン・ミリントン・シングによる戯曲。扇情的内容だったため初演時に暴動が発生した。を酷評する評論家に対する警句だ。
真夜中があたりに襲いかかると
不能者どもは地獄を抜けて集う
人で埋まった全ての通りで見つめられるは
偉大なるホワンの騎乗
こうした罵倒と憂慮があろうとも
彼のたくましいその足を見つめている
イェイツが自身の中に持つ力が彼に出来合いの比喩を与え、最後の行の激しい冷笑を生み出している。しかしこの短い詩でさえ六、七の不要な語がある。もしもっと整えられていれば、おそらくはさらに切れ味鋭いものになったことだろう。
メノン氏の本は意図せずイェイツの手短な伝記になっているが中でも彼がとりわけ興味を持っているのはイェイツの哲学「体系」で、彼の意見によるとそれは一般に認識されているよりもずっと多くのイェイツの詩に主題を与えている。この体系はさまざまな場所で断片的に説明されているが、その全容は展望という本で説明されている。これは自費出版された著作で私は一度も読んだことはないがメノン氏はここから多くを引用している。イェイツはその体系の起源について相矛盾する説明をおこなっていて、メノン氏は、形式上その基礎となっている「資料」は空想上のものだろうとかなりあからさまにほのめかしている。メノン氏は言う。イェイツの哲学体系は「ごく初期から彼の知的生活の背後に存在した。彼の詩にはそれが満ちている。それ無しでは彼の後期の詩はほとんど完全に理解不能なものとなる」。このいわゆる体系について読み始めるとすぐに私たちは大いなる車輪、還流、月の満ち欠け、転生、肉体なき魂、占星術といった呪術的なものの中に放り出される。これら全てを真剣に信じているのかについてイェイツは言葉を濁すが、彼が心霊主義と占星術に手を出していたことは間違いないし、また彼は若い頃に錬金術の実験をおこなうこともしていた。理解するのが非常に困難な月の位相に関する説明にほとんど埋もれかけているが、彼の哲学体系の中心思想は私たちにとって馴染み深い、循環宇宙論であるように思える。そこではあらゆるものが何度も繰り返されるのだ。おそらくイェイツの神秘主義信仰を笑う権利を持つ者はいないだろう……不思議な力に対するある程度の信仰はほとんど普遍的なものであることを証明できると私は思う……しかし、こうしたものをたいして重要でないたんなる奇行と書き飛ばすべきであることも間違いない。メノン氏の本で最も興味深いのはこのことに対する彼の認識である。「驚きと熱狂の最初のほとばしりにおいて」彼は言う。「ほとんどの人々は幻想的哲学を、偉大で興味深い知性のために支払わなければならない代償として片付けてしまう。自分がどこに向かっているのかに本当に気がつくことはないのだ。そして彼らはパウンドや、またおそらくはエリオットのようについには証言台に立つことを受け入れるのだ。予期されることだが、政治的思考を持つ英語圏の若い詩人からはこうしたものへの最初の反応は現れなかった。彼らは展望のそれよりも柔軟、あるいは人為的なところの少ない体系がイェイツ晩年のようなすばらしい詩を生み出さないことに頭を悩ませたのだ」。そんなことはないだろうが、メノン氏が指摘するようにイェイツの哲学にはいくつかの非常に不吉な含意がある。
政治的な言葉に翻訳すればイェイツの持つ傾向はファシストのそれなのだ。その人生のほとんどを通して、ファシズムという言葉が現れるずっと以前から彼は貴族的経路を介してファシズムにたどり着く人々と同じ考え方を持っていた。彼は民主主義、現代世界、科学、機械、進歩という概念……とりわけ人類の平等という思想をひどく憎む人間だった。彼の作品の心的イメージの多くは封建主義的であり、彼がありふれたスノッブさからまったく自由になれていないことは明らかだ。後になるとこうした傾向はよりはっきりとした形をとるようになり、それは彼に「唯一の解として独裁主義をおおいに喜んで支持する。暴力と専制といえどもそれらは必ずしも邪悪なものではない。なぜなら善悪を知らぬ人々は専制に完璧に黙従するようになるだろうからだ……全ては最上位から生まれるのだ。大衆から何かが生まれることはない」と言わしめた。政治にさして関心を持たず、また短期間だが政財界に関わったことで得た嫌悪にも関わらず、イェイツは政治的意見表明をしている。彼はリベラリズムの幻影を分かち合うには分別があり過ぎた人間であり、早くも一九二〇年にはある実に有名な詩(「再臨」)で私たちがまさに足を踏み入れつつある世界についての予言をおこなっている。しかし彼はその来たるべき時代、「階級的で男性的、苛烈で外科的」で、エズラ・パウンドとさまざまなイタリアのファシスト作家たちの両方から影響を受けたそれを歓迎しているように見える。自らが望み、信じる、到来するであろう新しい文明を彼は描写している。「その最上位の完成形に到達した貴族的文明。生活のあらゆる細部が階級的であり、夜明けには全ての偉大なる人の門戸に請願者が群れなし、あらゆる場所のおおいなる富がわずかな者の手にあり、全ての者がわずかな人々に仕える。皇帝その人でさえもさらに偉大な神に仕える神的従者なのだ。そして法廷で、家庭で、あらゆる場所で不平等によって法が作られる」。この発言の無邪気さはそのスノッブさと同じくらい興味深い。第一に「おおいなる富がわずかな者の手にあり」という一言でイェイツは、ファシズムの中心的現実を暴き出している。ファシズムのプロパガンダの全てはそれを覆い隠すためのものだというのにだ。たんなる政治的ファシストは常に自分たちは正義のために戦っていると主張する。詩人であるイェイツはファシズムが不正を意味することを一目で了解し、まさにそれを理由に称賛しているのだ。しかし同時に彼は、新しい独裁主義的文明はもしそれが到来したとしても貴族的なもの、あるいは貴族的という言葉で彼が意味しているものにはならないであろうことを理解できずにいる。それを統治するのはヴァン・ダイクヴァン・ダイク:アンソニー・ヴァン・ダイク。十六世紀の画家で、貴族・王族の肖像画を多く描いたことで知られる。風の顔をした貴族ではなく、匿名の億万長者、光沢のあるスーツを着た官僚、そして人殺しのならず者なのだ。同じ過ちを犯した他の者たちは後になって自分たちの見方を改めた。従って、もしもっと長生きしていたらたとえ心情だけとはいえイェイツは自分の友人であるパウンドの後に必ずや続いただろうと考えるべきではない。しかし先に私が引いた詩の持つ傾向は明らかで、過去二千年の間に達成された優れたものをことごとく放棄しようというその徹底ぶりは不安を覚える症状である。
イェイツの政治思想は彼のオカルト主義への傾倒とどのように結びついているのだろうか? なぜ民主主義への嫌悪と水晶占いを信じる傾向が共存するのかは一見したところ明らかではない。メノン氏はこれについてはごく短くしか議論していないが、二つの推測が可能だ。ひとつ目は、繰り返される周期に従って動く文明という理論は一方で人類の平等という概念を嫌悪する人々を求めるというものだ。仮にこの理論が正しければ「これら全て」、あるいはそれに似た何かが「以前にも起きていた」ことになる。そうなれば科学と現代世界は一撃で覆され、進歩は永遠に不可能なものへと変わる。下層階級の人々が自身を上昇させようとそれはたいした問題ではなく、結局の所、私たちはすぐに圧政の時代へと戻ることになるのだ。こうした考えを持つのは決してイェイツひとりではない。宇宙が車輪の上で円を描いて動いているとすれば、未来はおそらくその詳細まで予言可能なはずである。初期の天文学者が太陽年を発見したのと同じようにその動きの法則を発見するという問題に過ぎないのだ。そう信じれば、占星術やそれに似た体系を信じずにはいられなくなる。この戦争この戦争:第二次世界大戦を指すの一年前、フランスのファシストの週刊誌であり、陸軍将校によく読まれているグランゴワール誌の一部を調べている時に私はそこに三十八もの透視能力者の広告を見つけた。二つ目は、知識は秘密にされなければならない、それを知るのは認められた少数の仲間内に限られなければならないという思想がオカルト主義の中心概念にはあるということだ。同じ思想はファシズムにとっても不可欠なものだ。普通選挙権、普通教育、思想の自由、男女同権という展望を恐れる者たちは秘密カルトへの嗜好を持ち始めることだろう。ファシズムと魔術の間にはもうひとつ関連がある。両方ともカトリックの倫理規定に対して広く敵意を持つことだ。
イェイツがその信条において揺れ動いていて、その時々においてさまざまな異なる意見を抱いていることは疑いない。そこには進歩的なものも、そうでないものもある。メノン氏は彼のために、彼はこれまで生きてきたどの詩人よりも長い発達段階を経ているというエリオットの主張を繰り返している。しかし、少なくとも私が思い出せるだけの彼の作品の全てで変わらないように思えるものがひとつある。それは現代西洋文明に対する嫌悪と青銅器時代、あるいは中世かもしれないがそこへ戻りたいという欲求だ。こうした考えを持つ者の全てと同じように、彼には無知への称賛を描く傾向がある。彼の特筆すべき戯曲である砂時計に登場する痴者はチェスタートン風の人物、「神の痴者」、「生まれながらの罪なき者」であり、常に賢者よりも賢い。この戯曲の賢者はその全人生を費やした思考がまったくの無駄だったということを知って死ぬ(再び記憶から引用してみる)。
世界の流れはその道筋を変え
そしてその流れとともに私の思考も
濁った轟音の響く泉へと流れ込む
ああ、狂乱した頭を持つ者には
それも山麓の水源なのだ
私たちがなしたことは全て無に帰し
我らが思索も一陣の風しか残さぬ
美しい言葉だが、そこで示されているのはひどい蒙昧主義と反動である。そこで描かれているように村一番の白痴が賢者よりも賢いということが本当に真実だとすれば、アルファベットは決して考え出されることはなかったとした方がいいだろう。もちろん、あらゆる過去に対する称賛は私たちがその過去に生きていないために引き起こされる一時的感傷である。貧しい者は貧窮を称賛したりはしない。機械を嫌うにはその前に機械によって厳しい労働から解放されていなければならないのだ。しかしだからと言って、より原始的でより階級的な時代へのイェイツの憧れが本心からのものでないと言うわけではない。これら全てのうちのどれほどがたんなるスノッブさ、貴族の落ちぶれた子孫というイェイツ自身の立場の産物なのかはまた別の問題である。そして彼の蒙昧主義的な意見と彼の「古風で趣のある」言葉へ向かう傾向の間のつながりについてはいまだ解明途上である。メノン氏はそれについてほとんど触れようとしない。
これは実に短い本であり、私はメノン氏がさらに先に進み、この残された問題を取り上げたイェイツについての本をもう一冊書くところを見たいと強く望んでいる。「現代における最も偉大な詩人がファシズムの時代に大喜びで共鳴しているとすれば、それはいくぶん気がかりな兆候に思えることだろう」彼は最後のページでそう言ってそれっきりにしている。それが気がかりな兆候なのは、それが孤立した一例ではないからだ。全般に見て現代の最高の作家たちは反動的な傾向を持つ。たとえファシズムが何ら現実的な過去への回帰を提案していなくとも、過去に憧れる者たちはそのあり得るべき代替物よりはむしろファシズムを受け入れることだろう。しかし過去二、三年の間、私たちが見てきたように別のやり方も存在する。ファシズムと文学界の知識人の間の関係はおおいに調査を必要としていてイェイツはおそらくその開始点となるだろう。彼はメノン氏のような人物、つまり、詩人をまず第一に詩人として捉えることができ、しかし同時に作家の政治的・宗教的な信条は笑って済ませられる余分なものではなく、ほんの小さな細部であったとしてもその作品に痕跡を残す何かであることを理解している人物によってこそ最もうまく研究されるのだ。