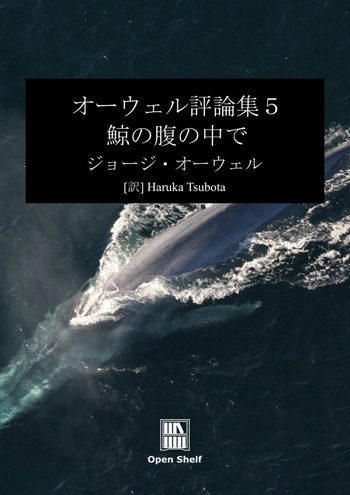チャールズ・リード
チャールズ・リードの作品が廉価版として出版されていることから見て彼にはまだ支持者がいると考えていいだろうが、自発的に彼の作品を読んでいる者に出会うことはめったにない。ほとんどの人にとって彼の名前はせいぜい学校の休暇中の課題として修道院と家庭に「取り組んだ」かすかな記憶を呼び覚ますものに過ぎないだろう。この特定の作品によって記憶されていることは彼の不運で、それはちょうどマーク・トウェインが映画のおかげで主としてアーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキーによって記憶されているのとまったく同様である。リードはいくつか退屈な作品を書いていて修道院と家庭はそのひとつなのだ。しかし彼は他にも三冊の小説を書いていて、私は個人的にはそれらがメレディスやジョージ・エリオットの全ての作品、また多芸多才やある盗賊の自叙伝といったいくつかのすばらしい中編小説よりも長い時を生き残る方に賭けたいと思っている。
リードの魅力とは何だろうか? 基本的にそれはR・オースティン・フリーマンの推理小説や少佐グールドの奇妙な物語集と同じ魅力……無益な知識の持つ魅力だ。リードは人が安っぽい百科事典的知識と呼ぶであろうものに特化した男だった。彼は脈絡のない情報の膨大な蓄えを持っていて、生き生きと語る才能によってそれを作品、少なくとも小説と呼べるような作品へと詰め込むことができた。もし日付けや帳簿、カタログ、具体的詳細、過程描写、ジャンクショップのショーウィンドウやエクスチェンジ・アンド・マート誌エクスチェンジ・アンド・マート誌:イギリスの週刊誌。自動車や楽器、家具を売りたい人の広告を掲載している。のバックナンバーに喜びを感じるような精神の持ち主であれば、中世の投石機がどのように動いたかを正確に知ることや一八四〇年代の監房にどういったものが置かれていたのかの全てを知ることを好む精神の持ち主であれば、リードを楽しまずにはいられないだろう。もちろん彼自身は自分の作品をこうした観点からは見ていなかった。自らの正確さに誇りを抱き、自身の作品の大部分を新聞の切り抜きから組み立てたが、集めた奇妙な事実は彼が自身の「目的」と見なしていたであろうものを補助するものだった。断片的にではあるが彼は社会改革主義者であり、瀉血や単調な仕事、私設の精神病院、聖職者の独身制、強く締め付けるコルセットといったさまざまな悪習に精力的な攻撃を加えている。
私自身のお気に入りはずっと変わらずファール・プレイで、偶然にもこの作品は特に何に対しても攻撃をしかけていない。十九世紀のほとんどの小説と同様、ファール・プレイは要約が難しいほど入り組んでいるが中心となる物語は若い聖職者ロバート・ペンフォールドにまつわるものだ。偽造にたいする不当な判決を受けた彼はオーストラリアへと移送されるが変装して逃亡し、遭難してヒロインとともに無人島に流れ着く。もちろんここでリードはその本領を発揮する。これまで生きてきた人間の中で彼は最も無人島の物語を書くのに適した人間だ。もちろん無人島の物語の中にもひどいものはあるが、生き残るための苦闘の真に迫った具体的詳細を丹念に描いている場合にはそれが完全にひどいものになることはない。遭難した人間の持ち物の一覧はおそらくフィクションの中で最も確実に人気がとれるもので、裁判の場面よりも確実だ。この作品を読んでから三十年近く経っているが、私はいまだにバレントンの珊瑚礁の島における三人の主人公の持ち物が何であったかをほぼ正確に思い出すことができる(望遠鏡、六ヤードの鞭縄、ペンナイフ、真鍮の指輪、帯鉄のかけらだ)。全体的に読みづらく、中には第二部が存在することさえ知らない者もいるロビンソン・クルーソーのような憂鬱な作品でさえ、クルーソーが苦労してテーブルを作ったり、土器に釉薬をかけたり、小麦畑を育てたりする様子が描写される時には愉快なものになる。一方でリードは無人島の専門家であり、そうでなくともともかく当時の地理学の教科書によく精通していた。さらに言えば彼は自身、無人島でくつろげるであろうタイプの人間だった。彼はクルーソーのように決してパンの発酵などといった簡単な問題に悩むことはなかっただろうし、バレントンとは異なり、文明化した人間が木の枝をこすり合わせて火をつけることなどできないと知っていた。
ファール・プレイの主人公はリードの描く主人公のほとんどと同じように一種のスーパーマンである。彼は英雄、聖人、学者、紳士、アスリート、ボクサー、探検家、生理学者、植物学者、鍛冶工、そして大工であり、それら全てがひとつに融合したもの、リードがイギリスの大学であれば通常は習得できると純粋に想像している全ての能力の一覧のようなものなのだ。言うまでもなく、このすばらしい聖職者がその無人島をまるでウェストエンドホテルのように変えるまでには一、二ヶ月しかかからない。その島にたどり着く前でさえ、難破船の最後の生存者たちが無甲板のボートで乾き死にしかけている時に彼は広口ビンと湯たんぽ、チューブの切れ端で蒸留装置を作ってその発明の才能を披露してみせるのだ。しかし中でも最高の一撃はその島を抜け出そうとする時のそのやり方だ。賞金首である彼自身は喜んで無人島生活を続けただろうが、彼が受刑者だとは思いもよらないヒロインのヘレン・ロールストーンはごく自然なこととして脱出を切望する。彼女はロバートにその「偉大な頭脳」をこの問題に向けるように頼む。もちろん最初の難題はこの島がどこにあるのかを正確に知ることだ。しかし幸運にもヘレンはまだ腕時計をしていて、それはまだシドニー時間を指していた。小枝を地面に固定してその影を見ることでロバートは太陽が最も高くなる正確な時間を記録する。それが済めば経度を求めるのは簡単な問題である……彼ほどの技量のあるものであればシドニーの経度を知っているのは自然なことだろう。同じように、彼が植生から一、二度の誤差で緯度を決定できることもごく自然なことだ。しかし次の難題は外界にメッセージを送ることだ。いくらか考えた後でロバートは密封された浮袋から作った羊皮紙の断片に、コチニールカイガラムシから採ったインクで一連のメッセージを書く。渡り鳥がこの島をよく居留地に使っていることに彼は気がついていて、最も適したメッセージの運び手として彼は鴨を選ぶ。鴨はどれでも遅かれ早かれ撃って取られるだろうからだ。インドでよく使われる仕掛けで彼はたくさんの鴨を捕まえ、それぞれの脚にメッセージを結びつけて放した。もちろん最終的にはその鴨の一羽が難を逃れて一隻の船に逃げ込み、二人は助け出される。しかしそこまで来て物語はようやく半分終わったところなのだ。この後に膨大な話の枝分かれ、筋書きとどんでん返し、陰謀、勝利と災難が続き、最後にはロバートの無実が証明されてウェディング・ベルが鳴り響く。
リードの三冊の最高の作品であるファール・プレイ、現金、改めるに遅すぎるは無しのいずれでも、第一の関心は技術的な細部にあると言っていいだろう。説明的な記述、とりわけ乱暴な行為の記述における彼の力もまた非常に際立ったもので、さらに続き物の物語であればというただし書きは必要だが彼はすばらしい筋書きを考え出す作家だ。彼には登場人物やあり得そうな出来事というものに対する一切のセンスが欠けているため、たんに小説家として見ると彼は真剣な考察の対象にはなり得ないが、彼自身は自らの物語の最も馬鹿げた細部でさえも信じ込めるという長所を持っていた。彼は自分の理解に従った人生を描き、多くのヴィクトリア朝時代の人間は同じように人生を理解していた。つまり常に善が勝利する続き物のすばらしいメロドラマとして理解していたのだ。今でも読むに値する全ての十九世紀の小説家の中でも、おそらく彼は自身の時代と完全に調和を遂げていた唯一の人間だろう。その非因習的な性格、その「目標」、不正を暴き出したいというその意欲にも関わらず、彼が根本的な批判をおこなうことは決してなかった。いくつかの表面的な邪悪を除けば彼は金銭と善、信心深い大金持ちとエラストス主義の聖職者を等しいものとする強欲な社会に何も悪いところは無いと考えていた。おそらくロバート・ペンフォールドの登場時のある事実以上に彼の価値観を理解させてくれるものはないだろう。ファール・プレイの冒頭で彼は、自分が学者であること、クリケット選手であることに触れ、ようやく三番目になってほとんど何気ない様子で神父であることを付け加えるのだ。
だからと言ってリードの社会的道義心のあり方が健全でなかったと言うわけではないし、いくらかの消極的なやり方で彼は世論を洗練させる助けになったはずだ。改めるに遅すぎるは無しでの刑務所制度への彼の攻撃は現代、あるいはごく最近の時代にも関係するし、その医療理論において彼は同時代のずっと先を行っていると言える。彼にまったく欠けているのは、その時代特有の価値体系を備えた初期の鉄道時代は永遠には続かないという観念だった。彼がウィンウッド・リードの兄弟であることを思い出せばこれは少々驚くべきことだ。急ごしらえでバランスが悪いながらウィンウッド・リードウィンウッド・リード:ウィリアム・ウィンウッド・リード。十九世紀イギリスの歴史家、探検家。の人類の苦難は現代的に見える。これは驚くほど幅広い展望を示して見せる著作で、おそらく今日、広く知られる「あらまし」の知られざる祖父母であろう。チャールズ・リードは骨相学、家具作り、鯨の習性の「あらまし」であれば書いただろうが、人類史については別だった。彼はたんに他の大多数より少しばかり良心に富んだ中流階級の紳士であり、たまたま古典よりは通俗科学を好んだ学者だったのだ。こうした理由から彼は私たちが手にとることのできる最高の「気晴らしのための」作家のひとりになった。例えばファール・プレイ、現金は塹壕戦の悲惨さに耐える兵士に送るのには良い本だろう。そこには何の問題提起も無いし、心からの「メッセージ」も無く、ただ、ごく狭い範囲の中で働く才能ある精神の持つ魅力、そしてチェスやジグソーパズルと同じような現実生活からの完璧な分離が提供されているだけなのだ。