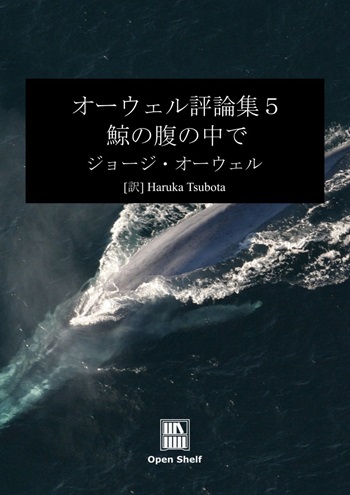詩とマイクロフォン
一年ほど前、私は他の数人と一緒に文学についての番組をインドに向けて放送する仕事をしていた。とりわけよく放送したのは現代・近現代の英語作家の詩だった……例えばエリオットエリオット:トマス・スターンズ・エリオット。イギリスの詩人、劇作家、文芸批評家。「荒地」などの著作がある。、ハーバート・リードハーバート・リード:サー・ハーバート・エドワード・リード。イギリスの詩人、文芸批評家、美術批評家。、オーデンオーデン:ウィスタン・ヒュー・オーデン。イギリス出身のアメリカの詩人。、スペンダースペンダー:スティーブン・スペンダー。イギリスの詩人、批評家。、ディラン・トマスディラン・トマス:イギリスの詩人、作家。詩「Do not go gentle into that good night」が特に有名。、ヘンリー・トリースヘンリー・トリース:イギリスの作家。「ヴァイキングの夜明け」、「青銅の剣」などの著作がある。、アレックス・コンフォートアレックス・コンフォート:イギリスの作家、医師。、ロバート・ブリッジズロバート・ブリッジズ:イギリスの詩人、劇作家、文芸批評家、医師。、エドマンド・ブランデンエドマンド・ブランデン:イギリスの詩人、文芸評論家。第一次大戦の従軍体験をテーマにした詩で知られる。、D・H・ローレンスD・H・ローレンス:デーヴィッド・ハーバート・ローレンス。イギリスの詩人、作家。「チャタレー夫人の恋人」などの著作がある。といった作家だ。可能な時にはいつでもその詩を書いた人々の協力を得て放送をおこなった。なぜそういった特殊な番組が設けられていたかはここで説明する必要もないだろうが(あのラジオ戦争における些細でまわりくどい側面攻撃だ)、私たちが放送で相手にしていたのがインドの聴衆であり、そのことが私たちのやり方をある程度規定していたことは付け加えておくべきだろう。私たちの文学放送がターゲットにしていたのはインドの大学生だったのだ。若くて敵対的な聴衆だ。イギリスのプロパガンダの可能性があるものには決して近づかない。どんなに多くとも聴衆が二、三千人を超えないことはあらかじめわかっていて、それが普段の放送よりも「高尚な」やり方をする口実を私たちに与えてくれた。
自分と同じ言語を理解はするものの文化的な背景は共有していない人々を相手に詩を放送する場合、ある程度の注釈と説明は避けて通ることができない。私たちが普段使っていた常套手段は月刊の文芸雑誌を模して放送するというものだった。オフィスで月刊誌の編集スタッフたちが次の号に何を掲載するかを議論しているという体だ。誰かが一編の詩を挙げ、他のもう一人が別のものを挙げる。短い議論の後、詩自体を取り上げて今までとは違う声、可能であれば作家自身の声で朗読するのだ。自然な流れで次の詩がそれに続く。そういう流れで番組は続いていった。普通はそれぞれの二編の詩ごとに少なくとも三十秒の議論がされた。三十分の番組で多くても六回の朗読がせいぜいだっただろう。こうしたたぐいの番組は必ずどこかしまりがなくなるものだが、ひとつの中心テーマを取り巻くようにすることで一定の統一感を演出することは可能だ。例えば私たちの想像上の雑誌のある号では戦争がテーマにされた。そこではエドマンド・ブランデンによる二編、オーデンの「一九四一年九月一九四一年九月:おそらく「一九三九年九月一日」の誤り。一九四二年に出版された詩集でこの詩が「一九四一年九月一日」と誤植されたことがあり、オーウェルはそれを参照していると思われる。」、G・S・フレイザーG・S・フレイザー:イギリスの詩人、文芸評論家。第二次大戦中、エジプトで情報活動に従事したことが知られている。による長編詩(「アン・ライドラーへの手紙」)からの抜粋、バイロンバイロン:ジョージ・ゴードン・バイロン。イギリスの詩人。の「ギリシャの島よ」そしてT・E・ローレンスT・E・ローレンス:トーマス・エドワード・ロレンス。イギリスの軍人、考古学者。映画『アラビアのロレンス』の主人公のモデル。の砂漠の反乱からの抜粋が取り上げられた。前後を議論で挟まれたこれら六編の詩は戦争に対してあり得る態度をなかなかうまく網羅している。これらの詩と散文で放送の二十分、議論でだいたい八分が占められた。
このやり方は少しばかり滑稽だし、かなり人を馬鹿にしたものだが、ちょっとした教育的な要素や教科書的な主題……真面目で、ときに「難解」な詩を放送しようとすれば避けて通ることのできないものだ……をくだけた議論として演出することでずっと身近にできるという利点がある。実際には聴衆に向かって言いたいことを何人かの話者が表面上は互いに話す体で言うことができるのだ。またこのようなアプローチによって少なくとも詩に対して文脈というものを与えることができる。これは平均的な人間の詩に対する視点からまったく欠けているものだ。だがもちろんやり方は他にもある。私たちがよく使っていた方法のひとつは音楽の中に詩を据えるというものだった。まず、これから数分の間、これこれの詩を放送するとアナウンスする。それから一分間ほど音楽をかけ、それがフェードアウトするのに合わせて題名や説明無しに詩を朗読する。それから再び音楽をフェードインさせて一、二分かける……全体で五分ほどの構成になる。音楽は適切なものを選ぶ必要がある。言うまでもないが音楽をかける真の目的は詩と番組の他の部分を分離することにある。私に言わせればこの方法によっていわば忌々しい不調和無しに三分間のニュース速報の中にシェイクスピアのソネットを埋め込むことができるのだ。
私が話してきたこれらの番組それ自体にはたいした価値はない。私がこういったものについて語っているのはそれが私に喚起させるアイデア、そして詩を広める方法としてのラジオの可能性といったもののためなのだ。詩を書いた本人による詩の放送がその聴衆だけでなく、程度の差はあれ詩人本人にも影響を与えるという事実はすぐさま私に強い印象を残した。ひとつ心に留めて置かなければならないのはイギリスにおいては詩の放送がおこなわれることは極めて少なく、またイギリスの詩人の多くは声に出してそれを朗読するなど考えたこともなかったということだ。マイクの前に座ることによって詩人は自分の詩作と新しい関係性を結ぶことになる。とりわけそれが定期的におこなわれる場合にはそうだ。これは今この時代、この国でなければ起き得ないことだ。近代……つまりここ二百年ほどの間……において詩は時を追うごとに音楽や話し言葉とのつながりを薄れさせていくのが普通だった。存在するためにはとにかく出版されることが必要で、もはやそれ自体がどのように吟じられたり、あるいは朗読されるかさえ詩人が知ることは期待できなかった。どのように天井にしっくいが塗られるのか建築家が知ることができないという状況よりもなおひどい。叙情や美辞にあふれた詩はもはやほとんど書かれなくなり、識字率の高い国ではどこでも一般の人々の詩に対する嫌悪が日常的なものになった。そしてひとたびそういったほころびが生まれた場所ではその勢力は広がる一方だった。詩とは印刷されたものであり、ごく少数の者だけが理解できる何か曖昧さや「小利口さ」を促進するものであると考えられたのだ。一目見て意味がわかる詩はどこかおかしいのだという半ば本能的な感覚から自由な人間がいったいどれほどいるだろうか? 詩を声に出して読むことが再び普通のことにならない限りこういった傾向がおさまることはなさそうに思えるし、ラジオというメディアを使わずにそれを実現する方法を見つけ出すことは難しいだろう。だがラジオのとりわけ優れた点は正しい聴衆を選別するその力であり、人前で話す緊張やきまり悪さを取り除く力であるという点はここで強調しておきたい。
放送では当然その聴衆の存在を想定するものだが、実のところそれはたった一人のリスナーなのだ。百万人が耳を傾けてはいるかもしれないがそのそれぞれは一人か、あるいはごく少数の人間からなる集団であり、皆、あなたが自分個人に語りかけている(あるいはそうあるべきだ)という感覚を抱いている。さらに言えば聴衆が放送に共感を覚えていること、少なくとも興味を持っていると考えるのはもっともなことだろう。退屈している者は誰でもスイッチをひねって即座にあなたを締め出すことができるのだ。だが共感を覚えてはいても聴衆はあなたに対して無力だ。放送が演説や講義と異なるのはまさにそこなのだ。演説に慣れた者であれば誰しも知るように舞台の上で聴衆に調子を合わせないでいることはほとんど不可能といってよい。どんな場合であれ数分もあれば聴衆が何に反応し、何に反応しないかが明らかになり、そこにいるもっとも愚かそうな人間にもわかるような話し方をせざるを得なくなる。そして「パーソナリティ」として知られるあの宣伝手法に取り込まれてしまうのだ。もしそうしなければその場は決まって凍りついたような困惑の空気に包まれる。あの「詩の朗読会」という代物が悲惨なものになるのは退屈していたり実のところ敵意しかない聴衆が紛れ込んでしまうこと、そして彼らが手軽にスイッチをひねって退出できないためなのだ。これはイギリスでは正式な形でシェイクスピアの舞台をおこなえないという問題……演劇の観客が選別されていないと言う事実……と根本においては同じだ。放送ではこのような状況は存在しない。詩人は詩になにがしかの意味を見出している人々に向かって話をしていると感じるし、放送に慣れた詩人はマイクに向かってすばらしい技術で朗読できる。もし目の前に目に見える形で聴衆がいたらとても同じようにはできないだろう。先に紹介したようなごっこ遊び的な要素はたいして重要ではない。重要なのは現在可能な唯一の方法によって詩が声に出して読まれるという状況が現れたことだ。しかも一見したところ自然できまり悪さのない、人と人の日常のやりとりという形でそれはおこなわれるのだ。さらに詩人は自分の作品を紙の上の記号の羅列でなく音として考えるようになり始めている。これによって詩と普通の人々との間の和解はよりいっそう現実に近くなった。電波の一方の側にいる詩人ではすでにそれが起きているのだ。いずれは同じことが反対側でも起きるだろう。
しかし、だからといってそのもう片方の側で現在何が起きているかに目を向けずに済ますわけにはいかない。ここまで私が、詩全体は厄介な状態、ほとんど破廉恥とも言える状態にあると言ってきたように感じるかもしれない。そして詩を広めることこそが子供に薬を飲ませたり、迫害を受けている集団に対する寛容さを実現するのと同じく欠かすことの出来ない戦略的行動であると主張しているように思われるかもしれない。だが残念なことにこれが現実なのだ。現在社会において詩こそが芸術の名をもっとも傷つけていることは疑いようがないだろう。平均的な人間がその価値を認めようとしないただひとつの芸術形態が詩であることは間違いない。英語が話される国において「詩」という言葉は放水ホースよりも迅速に群集を追い散らすだろうとアーノルド・ベネットアーノルド・ベネット:イギリスの小説家、劇作家、批評家。は言ったが、そこにはほとんど何の誇張もない。そして私がすでに指摘したようにいったんそれが生じればこの種のほころびは広がりつづける傾向にある。普通の人間はますます詩を嫌い、詩人はますます尊大で理解し難いものになってゆき、当然の成り行きとして最後には詩と大衆文化が完全に分離してしまうだろう。詩が存在するのはこの時代、この地球上のごく限られた地域のみであると言うのにだ。高度に文明化された国々に住む平均的な人間がもっとも粗野な未開人よりも劣った審美眼しか持たない時代、私たちが生きるのはそういう時代なのだ。こうした状況は全体的に見て意識的な活動によっては修正不能に思われるが、一方で社会が魅力的な形をとればすぐにでも自発的に正されそうにも思われる。まるでマルクス主義者や無政府主義者、特定の宗教の信奉者の説教のようだが大筋においてそれが真実であることは疑いようがない。私たちの生活を囲む醜さには精神的原因や経済的原因があり、それはたんに何かの伝統を見失っているということでは説明できない。だが現在の私たちが持つ枠組みの中でその改善が不可能というわけではない。審美的な改善は社会を取り戻す行為の中の必要不可欠な一部なのだ。だからこそ詩をもっとも嫌われている芸術という特別な位置から救い出すことはできないと考えたり、音楽と同じ程度に受け入れられるようにすることは不可能なのではないかと疑うのはやめるべきだ。だがまず最初に質問をしておく必要はある。詩はどのように、そしてどれくらい嫌われているのだろうか?
一見したところ、詩の不人気は極限にまで達しているように見える。だがよく考えてみればその嫌われ方は非常に限定されたものだ。まず第一に伝統的な民族詩(わらべ歌といったものだ)はまだかなり多く残っている。それらは広く人々に知られ、引用され、脳裏に刻まれている。他にも一握りの古代の歌や叙事詩がある。それらが人気を失うことは決してない。それに加えて評判のいい、あるいは少なくとも受け入れられていると言える「優れた俗悪」詩がある。全体的には愛国心や感傷を煽るようなたぐいのものだ。平均的人間が詩を嫌う原因となる性質とこの「優れた俗悪」詩が表面的には無縁なのだと考えるとそれは的を外した議論になるだろう。節回し、押韻、もったいぶった修辞や見慣れない言葉……これら全てが過度に使われている。そのためほとんどひと目でこれら低俗詩が良質な詩よりもずっと「詩的」であることがわかる。しかしそういった分かりやすいもの以外でも受け入れられているものがある。例えばこの記事を書く直前まで私はBBCでコメディアンが話すのを聞いていた。九時のニュースの前のおなじみのショーだ。終わりの三分間で二人のコメディアンのうちの一人が突然「少し真面目な話をしたい」と言いだし、「良き古き英国紳士」と題された愛国的なたわ言の朗読を始めた。内容は我らが国王我らが国王:イギリス国王ジョージ6世を指す。を褒め称えるものだ。さて唐突に繰り広げられたこのリズム付きの英雄詩のまがい物に聴衆はどのような反応をするだろうか? 強烈に否定的な反応が起きるとは思えない。BBCのこういった放送をやめさせるために抗議の投書が殺到するということもなさそうだ。ここから下せる結論はこうだ。大衆は詩を嫌っているが、韻文をひどく嫌っているわけではない。押韻や韻律そのものが嫌われているのであれば、歌や品のない滑稽五行詩が人気になることなどないはずだ。詩が嫌われているのはそれが不明瞭で、お高くとまっていると思われているからだ。場違いなその雰囲気のためなのだ。詩という言葉は「神」や牧師の詰め襟といった言葉と同じ種類の不快な印象を想起させるのだ。詩を広めるということはある意味で後天的に獲得された抑制をいかにうち消すかという問題なのだ。人々に機械的な軽蔑のうめき声を発せさせるのではなく、耳を傾けさせるにはどうすればいいのかという問題なのだ。もしちゃんとした詩を普通に見えるやり方、つまり私が耳にしたあのたわ言のように大衆にとって身近なものにできれば詩に対する先入観の一部は克服できるだろう。
一般の人々の好みを育んでいくという地道な努力無しに詩が再び人気を取り戻すことは考えにくい。そしてその努力は戦略的におこなう必要がある。おそらくはごまかしといえる行為さえ必要だろう。T・S・エリオットはかつて詩、とりわけ舞台劇に使われる詩は大衆演劇場というメディアを通じて一般の人々の意識へと入り込んでいくのだろうと示唆した。また彼であれば無言劇はその広大な可能性をいまだ完全には探求し尽くされていないように思われると付け加えたかもしれない。おそらく「闘士スウィーニー闘士スウィーニー:T・S・エリオットによる詩劇。1933年に途中まで書かれた状態で上演されるが結局、未完に終わった。」はそのような着想によって書かれている。実際、その戯曲からは大衆演劇場の雰囲気を、少なくとも歌劇の一場面を連想させられる。ラジオが非常に有望なメディアであることはすでに述べたし、その技術的な利点、とりわけ詩という観点から見た利点についても指摘した通りだ。初めてこの指摘を耳にする人にはそらぞらしく聞こえるだろう。それはくだらないたわ言以外のものを広めるためにラジオを利用できると想像できる人間が少ないからだ。大声でわめく世界中の演説者の口から吐き出されるたわ言を耳にして人々は無線電信機にはそれ以外に使い道など無いと結論してしまっている。確かに「ワイヤレス」という言葉からはわめきちらす独裁者か、三つの空港の奪還に失敗したとアナウンスする落ち着いたしわがれ声を連想せずにはいられない。詩の放送と聞けばまるでストライプのズボンを履いた女神のようだと思うだろう。しかし、だからと言ってある道具の持つ可能性とその道具の現在の使われ方を一緒くたにするべきではない。放送は今、その状況にある。原因はマイクやトランスミッターといった器具全体の持つ本質的な野蛮さ、馬鹿馬鹿しさ、いいかげんさではない。現在、世界中で繰り広げられている放送の全てが政府や独占企業のコントロールの下にあること、それら組織が現状を維持するという自らの目的のために普通の人々が過度に知的になることを妨げていることこそが原因なのだ。それと同じようなことは映画でも起きている。ラジオと同じく映画も資本主義による独占段階にあるように見える。その経営には途方も無い財力が必要だ。全ての芸術形態で似たような傾向が見られる。役人のコントロール下に入るチャンネルは増える一方だ。彼らの目標は芸術家を叩きのめすこと、少なくとも骨抜きにすることである。現在、世界中の国で進行しつつあり、また疑いなくこれからも進行していくであろう全体主義的傾向が別の変化によって緩和されない限り見通しは暗いだろう。その変化が何なのか、たった五年先のことであっても予見することは難しい。
私たち全員がその一部であるこの巨大な官僚機構が今、規模と持続的な成長を求めてきしむような音をたてながら動き始めている。近代国家には知的自由を排除しようとする傾向がある。それと同時に全ての国家、とりわけ戦争の脅威にさらされている国家はますます国家のための宣伝活動をおこなう知識人の必要性を感じるようになっている。例えば近代国家はパンフレットの執筆者、ポスターを描く芸術家、イラストレーター、アナウンサー、講演家、映像作家、役者、作曲家、さらには画家や彫刻家さえも必要としている。心理学者や社会学者、生化学者、数学者などについては言うまでもないだろう。今の戦争を始める時、イギリス政府は文学界の知識人たちをそこから締め出そうという意図をたいして隠そうともしなかった。だが戦争開始から三年が過ぎた後、ほとんど全ての作家がその望ましからざる政治遍歴と見解にも関わらずさまざまな省庁やBBC、さらには軍隊にさえ飲み込まれていった。それら組織はようやく自身が宣伝活動やその他の必要不可欠な文章仕事を抱えていることに気がつき始めたのだ。政府は不承不承ながらもそういった知識人たちを取り込んでいった。彼ら無しでは物事がうまく進まないことに気がついたからだ。当局からしてみれば宣伝は全てA・P・ハーバートA・P・ハーバート:アラン・パトリック・ハーバート。イギリスのユーモア作家、小説家、劇作家。法改革活動家としても知られる。やイアン・ヘイイアン・ヘイ:イギリスの小説家、劇作家、エッセイスト、歴史家。教師、軍人としても知られるジョン・ヘイ・ビースのペンネーム。のような「安全」な人々に任せるのが理想だろう。しかしその手の仕事に使える人間はそう多くはない。すでに知られている知識人を使わざるを得ないのだ。結果、当局のプロパガンダの色合いや、さらにはその内容さえもある程度は変わっていった。過去二年間に被占領国に向けて作られた政府のパンフレットやABCA(時事軍事局)による講演、ドキュメント映画、放送を見れば、それが自らの助けになると思って我らが統治者がそれに出資したのだろうと考える者は一人もいないだろう。ただ政府機関をより強大にし、際限なく仕事を増やし、目的を忘れ去っていったのだ。これは下劣な行為というよりはむしろわずかな救いと言える。すでに自由主義的な伝統を強く持つ国では官僚的な専制が完全なものになることは決して無いということを意味するからだ。統治するのはストライプのズボンを履いた者たちだろうが彼らが知識人を必要とする限り、知識人たちはかなりの程度、自律的に振る舞うことができるのだ。例えばもし政府がドキュメント映画を必要とすれば撮影技術にとりわけ強い関心を抱く人々を雇い、必要最低限の自由は許容せざるを得ない。かくして官僚的な視点から見ればひどい出来の映画が常に立ち現れ続けることになる。絵画や写真、台本書き、ルポタージュ、講演やその他の芸術、それに複雑な近代国家が必要とする芸術に類する活動についてもそれは同じことだ。
これがラジオの場合にも当てはまることは明らかである。現在のところ、この拡声器は創造的な作家の敵であるが、放送の量と適用範囲が増えていけばいつまでもこのままではないだろう。とはいえ今のところはBBCが現代文学に示す関心は弱々しいままである。詩の放送を五分でも耳にするのは難しい一方で嘘にまみれたプロパガンダや安っぽい音楽、くだらないジョークややらせの「議論」といったものは十二時間でも耳にすることができる。だがこの状況も私が示したように変わっていくだろうし、その時には現在妨げになっているさまざまな敵対的影響を完全に無視して詩の放送で真剣な実験をおこなうことが可能になるだろう。私はそのような実験によってとてつもなくすばらしい結果が得られるだろうと言いたいわけではない。ラジオはその歴史の中であまりに早く官僚化され、そのために放送と文学の間の関係は十分に検討されてこなかった。マイクロフォンによって詩を普通の人々の手に取り戻すことができるかどうかは定かでないし、文字で書かれるものから声に出して読まれるものになることで詩が力を得られるかどうかさえ確かなことは言えない。だがその可能性があるということは強調しておきたい。そして文学を愛す者はもっとこの嫌われ者のメディアに目を向けるべきだ。それが持つ好ましい力はおそらくはジョード教授ジョード教授:シリル・エドウィン・ミチンソン・ジョード。イギリスの哲学者、放送パーソナリティ。第二次大戦中に放送された討論番組で人気を博すが1948年に無賃乗車スキャンダルを起こしてその地位を失う。とゲッベルス博士ゲッベルス博士:ヨーゼフ・ゲッベルス。ドイツ・ナチの宣伝大臣を務める。の声によって覆い隠されているのだ。