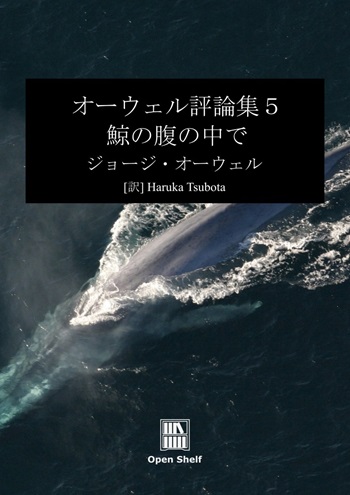第一章
ヘンリー・ミラーの小説である北回帰線が一九三五年に登場した時、それはためらいがちな称賛によって迎えられた。いくつかの例ではポルノを楽しんでいると見られることへの恐怖によってそうした態度が取られたことは明らかだった。この作品を称賛した人々はT・S・エリオット、ハーバート・リード、オルダス・ハクスリー、ジョン・ドス・パソス、エズラ・パウンドといった者たち……全体的には現在の流行作家とは言えない者たちだった。そして実際のところ、この作品のテーマ、またそれが持つ精神的雰囲気のいくらかは三十年代というより二十年代に属している。
北回帰線は一人称で書かれた小説、あるいは小説形式の自叙伝であり、どちらとも好きなように取れる。ミラー自身はまごうことなき自叙伝であると主張しているが、物語の語り口調と手法は小説のそれである。物語はパリに住むアメリカ人についてのものだが、ありきたりな筋書きとは異なっている。そこに関わってくるアメリカ人たちは偶然にも金を持っていない人々なのだ。好景気の間、ドルが潤沢でフランの為替価格が安かったころにはパリはこうした芸術家、作家、学生、好事家、観光客、道楽者、まったくの怠け者の群れであふれていて、おそらくそれはこれまで世界が目にしたことのない規模のものだった。いくつかの街区ではいわゆる芸術家と呼ばれる者たちが労働者の人口を完全にしのいでいたことはまず間違いない……思うに二十年代後半のパリには三万人ほどの画家がいて、その大半が詐欺師だったのではないだろうか。そうした人々があまりに急激に増えたため、コーデュロイのブリーチーズ・パンツを履いたしわがれ声のレズビアンやギリシャ時代か中世のような装いの若い男からなる芸術家たちが通りを歩いても視線を集めることは無かったし、セーヌ河岸に沿ったノートルダムでは座ってスケッチを描く人の視線を横切らずに歩くことは不可能なほどだった。ダークホースと無名の天才の時代であり、皆の口に上る文句は「いつかは自分も一旗あげる」だったが、結局のところ「一旗あげた」者は誰もいなかった。その衰退はまるで氷河期の再来のようだった。コスモポリタンな芸術家の一群は消え失せ、ほんの十年前には叫び声を上げる目立ちたがり屋たちで明け方まで埋まっていた巨大なモンパルナスのカフェは幽霊さえ現れない薄暗い墓地へと変わった。これが……ウィンダム・ルイスのターといったさまざまな他の小説でも描写された……ミラーの描く世界だが、彼が扱っているのはその低層の部分だけ、つまり一部は真の天才、一部は真のろくでなしから成り立っていたためにこの衰退期を生き残ることができたルンペンプロレタリアートの非主流派についてだけである。無名の天才、プルーストを完全に打ちのめす小説を常に執筆「予定」のパラノイアが登場するが、彼らが天才的であるのは次の食事を探し回っていない滅多にない瞬間だけのことである。物語のほとんどは労働者向け宿泊所の虫だらけの部屋、けんか、酒盛り、安い売春宿、ロシアからの亡命者、たかり、詐欺、日雇い仕事についてだ。そしてパリの貧民街に漂う全体的な雰囲気はひとりの外国人から見たそれである……石畳の路地、ごみから漂う酸っぱい臭い、油っぽい亜鉛メッキのカウンターとすり減ったレンガの床の安酒場、セーヌ川の緑色の水、フランス共和国親衛隊の青いマント、崩れかかった鉄製の小便器、メトロの駅独特の甘い匂い、ばらばらにちぎれるタバコ、リュクサンブール公園の鳩……全てがある。少なくともそれが感じられるのだ。
表面的には危ういものは何も無かった。北回帰線が出版された当時、イタリア人たちはアビシニアへ侵攻し、ヒトラーの強制収容所はすでに膨れ上がっていた。世界の知識人たちが焦点を合わせていたのはローマ、モスクワ、ベルリンであり、当時はラテン区ラテン区:パリのセーヌ川の河岸の5区および6区の一部で、教育機関が集中する文教地区で酒をたかるアメリカ人の怠け者について書くことが小説の比類なき価値であるとは誰も考えていなかった。もちろん小説家に現代史を直接的に書く義務があるわけではないが、その時代における大きな出来事を完全に無視する小説家は物の価値がわからないか、あるいはたんなる愚か者だ。北回帰線の扱う題材について説明を聞いただけではほとんどの人はそれを二十年代の下品な思い出話としか考えないだろう。実際に読んでみればそうではなく極めて優れた作品であることにほとんど全ての人がすぐ気がつくはずだ。どのように、そしてなぜ優れていると言えるのだろう? この質問には簡単に答えることができない。まず北回帰線が私自身の頭に残した印象について説明することから始めた方がいいだろう。
初めて北回帰線を開き、そこに文字にできないような言葉が満ちていることを見て取った時、私のとった瞬間的な反応は感銘を受けることの拒否だった。ほとんどの人が同じだろうと思う。それにも関わらず時間をおいてみると無数の細々したものを脇におけば、その作品の持つ雰囲気は奇妙に私の記憶に残るように思えた。一年後、ミラーの二冊目の作品である黒い春が出版された。その時はどうだっただろうか? 北回帰線は最初に読んだ時よりもずっと鮮明に私の頭の中に存在していた。黒い春に対する第一印象は、衰えが見られること、そして前の一冊のようなまとまりに欠けていることだった。しかしさらに一年経ってみると黒い春の中の多くの文章がまたしても私の記憶の中に根付いていたのだ。明らかにこれらの作品は背後に香りを残していく種類のもの……「それ独自の世界を作り上げる」作品なのだ。これを成し遂げる作品は必ずしも良書ではなく、ラッフルズやシャーロック・ホームズの物語のような良い悪書であったり、嵐が丘や緑の鎧戸の家のような倒錯した病的な作品であることもある。しかしときおり、奇妙なものでなく、よく見知ったものを明らかにすることで新しい世界を切り開く小説が現れるのだ。例えばユリシーズで真に卓越しているのはその題材の平凡さである。もちろんユリシーズには他にも多くのものが含まれている。ジョイスが一種の詩人であり、またとてつもない衒学者であったためだ。しかし彼の本当の功績はありふれたものを紙の上に書き記したことなのだ。彼はあえて……それは技術と同じくらい勇敢さが必要なことだ……頭の中の愚かしさをさらけ出し、そうすることで皆にとって身近だったアメリカを暴き出したのだ。ここに事物の世界が存在する。それらは本質的に言葉では説明できないように思えるが、ある者はなんとかそれを言葉にしようとする。その結果、少なくともしばらくの間は人間がその中で暮らす孤独が打ち崩されるのだ。ユリシーズのいくつかの文章を読めばジョイスの思考と自分の思考がひとつであり、自分の名さえ知らない彼が自分の全てを知っている、時空の外側に自分と彼が共にいる何らかの世界があると感じるだろう。そして他の点ではジョイスと似ても似つかないにも関わらず、こうした性質の感触がヘンリー・ミラーにはあるのだ。全ての個所でというわけではない。彼の作品は非常にむらがあり、とりわけ黒い春ではときおりかなり冗長な言い回しや超現実主義的で支離滅裂な世界へと逸れていく傾向がある。しかし五ページ、十ページ、彼を読んで欲しい。奇妙な安心を感じるだろう。それは理解したからというよりも理解されたからなのだ。「彼は私の全てを知っている」と感じる。「彼は特別に私のためにこれを書いたのだ」。あたかも自分に話しかける声が聞こえるようだ。親しげなアメリカ人の声。そこにはごまかしも道徳的な目的もなく、ただ私たちは皆、似通っているのだという暗黙の前提があるだけだ。しばらくの間、嘘や単純化、型にはまった人形じみた性質のありきたりなフィクション……たとえそれが実に優れたフィクションであろうとも……から離れ、はっきりとした人間の経験を手にとることになる。
しかしそれはどのような種類の経験だろうか? どのような種類の人間だろうか? ミラーが書くのは通りに立つ男だ。しかも極めて残念なことに同じような仲間が大勢いる通りに立っている。それは自身の生まれ育った地を離れた報いなのだ。それが意味するのは自身の根を貧相な土壌に移し替えるということなのだ。おそらく国外追放は小説家にとって画家や、あるいは詩人とさえ比較してもずっとひどい傷を与える。なぜなら職業生活から切り離され、その行動範囲を通りやカフェ、教会、売春宿、スタジオへ狭めてしまうからだ。全体的に言えばミラーの作品で目にすることになるのは国外生活を送る人々、酒を飲み、語り、瞑想し、情事に励む人々であって、働き、結婚し、子供を育てる人々ではない。残念なことだ。彼も他の者と同じようにひと揃いの活動を描き出したいと思っているのだ。黒い春にはニューヨークの素晴らしい回想場面がある。O・ヘンリーの時代のアイルランド移民が群れ集うニューヨークだ。しかし最も卓越しているのはパリの場面である。社交家としてはまったくの役立たずであることは認めざるを得ないが、そこで描かれる酔っぱらいとカフェに集う無気力な者たちは人物造形のセンスと技術的熟達によって取り回され、それは近年のどの小説も寄せつけないものである。全てがもっともらしいというだけでなく、完璧に見知ったものなのだ。描かれる全ての冒険が自分の身に起きたかのように感じられることだろう。冒険の内容にはひどく驚かされるものは何も無い。ヘンリーは陰鬱なインド人学生と共に職を得て、急な寒波が来てトイレが固く凍りつく時期にひどく不快なフランスの学校でもうひとつ職を得る。友人の船長コリンズとル・アーヴルでの酒宴に出かける。すばらしい黒人女性のいる売春宿へ出かける。友人の小説家ヴァン・ノードンと語り合う。彼は世界に関するとてつもない小説を頭の中に抱えているがどうしてもそれを書き始めることができないでいる。飢餓に瀕している友人であるカールは彼との結婚を望む裕福な未亡人に拾われる。長々としたハムレット調の会話が繰り広げられ、そこでカールは飢えるのと老いた女性と寝るののどちらが悪いか決断しようとする。未亡人を訪ねる彼の様子がひどく詳細に描かれる。一番いい服を着た彼がどのようにホテルを訪れたのか、訪れる前にどのように尿意を無視したのか、それゆえにその夜全体が苦しみの長い絶頂となったことなどなどだ。そうして結局のところ、それはひとつも真実でなく未亡人は存在さえしない……カールが自らを重要人物に見せるために彼女をでっち上げただけなのだ。この作品全体が多かれ少なかれこうした調子である。なぜこうしたとてつもない些末事が心を奪うのだろう? まさに全体の雰囲気が深く見慣れたものであるため、それを読んでいる間ずっとそうした出来事が自身に起きているかのように感じられるためなのだ。そしてこうした気分を感じられるのはありきたりな小説のジュネーヴ条約的な言語を破棄し、頭の中の現実政治をおおやけに引きずり出すことを選んだためなのだ。ミラーの場合、その思考メカニズムを探ればそれが平凡な事実と平凡な感情の告白であることにあまり疑問の余地はない。実のところを言えば多くの平凡な人々、おそらく大多数の者はまさにここで記録されているようなやり方で話し、振る舞っている。北回帰線の登場人物の話し方に見られる冷淡な粗野さはフィクションにおいては非常に珍しいものだが現実生活では極めてありふれたものだ。自分たちが粗野な話し方をしていると気づいてさえいない人々がする、まさにこのような会話を私は何度も耳にしてきた。北回帰線が若い男の書いた作品でないことを指摘しておくことには価値があるだろう。この作品が出版された時、ミラーは四十代だった。以来、彼は三、四冊の作品を産み出しているにも関わらず、この最初の作品が何年も彼につきまとっていることは明らかである。これは自分たちが何をしているか知っていてそれゆえに待つことができる人々によって書かれた、貧困と無名の中でゆっくりと熟成されていく作品のひとつなのだ。その散文は驚くべきものであり、黒い春の一部ではさらに優れたものになってさえいる。残念ながらそれをここに引用することはできない。文字にできないような言葉がいたるところに現れるのだ。しかし北回帰線を、黒い春をぜひ手に入れて、とりわけ最初の百ページを読んでみて欲しい。英語の散文で何ができるのかについて今に至っても着想を与えてくれるだろう。そこでは英語は話し言葉として扱われている。ただし恐れ、つまり修辞や普通でないこと、詩的な言葉への恐れを知らない話し言葉だ。形容詞が十年の追放の後に戻ってきたのだ。流れうねる散文、リズムを持った散文、平板で慎重な声明文や現在の流行りのお手軽な方言とはまったく異なるものである。
北回帰線のような作品が現れる時、最初に人々の目に留まるのがそのわいせつ性であるのは実に自然なことだ。私たちの現在の文学的良識の観念のもとでは文字にできないような作品に超然とした態度で近づくことはそう簡単ではない。衝撃を受けて嫌悪を覚えるか、病的な興奮を覚えるか、さもなくば何ら評価すべき点はないと判断するかなのだ。おそらく最後のものが最も一般的な反応で、その結果、文字にできないような作品は本来得られるよりも少ない関心しか得られないことがしばしばある。わいせつな作品を書くより簡単なことはない、話題を集め金儲けをする目的のためだけにそういった作品は書かれるのだなどと語ることがおおいに流行っている。そうでないことは警察裁判所でわいせつとされるような作品にまったく人気が無いことからも明らかである。汚い言葉を使えば簡単に金が手に入るというのであれば、もっと多くの人々がそれをやっているだろう。「わいせつ」な作品があまり頻繁には現れないためにそれらをひとまとめに扱う傾向があるのだ。一般にはこれはまったく不当なことだ。北回帰線はおおまかに言って二つの別の作品と関連を持っている。ユリシーズと夜の果てへの旅夜の果てへの旅:フランスの作家ルイ=フェルディナン・セリーヌによる小説だ。しかしどちらともあまり類似点は多くない。ミラーがジョイスと共通しているのは無意味で卑しい日常生活について語ろうという意志である。技術的な違いを脇におけば、例えばユリシーズの葬式の場面は北回帰線によく合うことだろう。その章全体がいわば告白、人間の恐ろしい内的冷淡さをさらけ出すものなのだ。しかし似ているのはそこまでである。小説として見ると北回帰線はユリシーズに遠く及ばない。ジョイスは芸術家であるが、そうした意味で言えばミラーはそうではないし、おそらくそれを望んでもいないだろう。あらゆる点でジョイスの方がずっと多くを試みている。彼は意識、夢、空想(「金のブロンズ」の章「金のブロンズ」の章:ユリシーズの第二部十一挿話「セイレーン」を指す )、酩酊などのさまざまな状態を探索し、それら全てをひとつの巨大で複雑なパターン、ほとんどヴィクトリア朝的「筋書き」につなぎ合わせているのだ。ミラーは人生について語るたんなるハードボイルドな人物、知的勇敢さと言葉の才能を持ったごく普通のアメリカ人ビジネスマンに過ぎない。彼がまさに誰もが頭に思い浮かべるアメリカ人ビジネスマンそのままであることにはおそらく意味があるだろう。夜の果てへの旅と比較した場合にはこうした違いはさらに大きくなる。どちらの作品も文字にできないような言葉を使い、どちらもある意味で自叙伝である。しかしそれが全てだ。夜の果てへの旅は目的を持って書かれた作品で、その目的とは現代生活……実際のところは人生……の恐ろしさと無意味さに抗議の声を上げることだ。それは耐え難い嫌悪の叫び、汚水槽からの声だ。北回帰線はほとんど完全にそれの反対である。事態はほとんど異常とも思えるほど普通でない状態になるが、これは幸福な男についての作品なのだ。望郷の色合いを帯びているためにわずかにその程度が減じてはいるが黒い春も同じだ。その背後にある長年のルンペンプロレタリアート生活、飢え、放浪、汚物、失敗、野外で過ごす夜、出入国審査官との戦い、わずかな現金をめぐる終わることの無い奮闘によって、ミラーは自分が自分自身を楽しんでいることに気がついたのだ。セリーヌが恐怖を感じたまさにそれと同じ人生の側面が彼にとっては魅力的に写った。抗議どころか彼は受け入れたのだ。そしてまさにこの「受容」という言葉は彼の本当の類縁であるもうひとりのアメリカ人、ウォルト・ホイットマンを思い起こさせる。
しかし一九三〇年代においてホイットマンであることには実に興味深い何かがある。もしホイットマン自身が現在生きていたとして、彼が草の葉に少しでも似たものを書くかどうかは定かでない。究極的に彼が語っていたのは「私は受け入れる」ということであるが、現在の受容と当時の受容の間には根本的な違いが存在する。ホイットマンが執筆をおこなったのは前例のない繁栄の時代だったが、さらに重要なのは彼が執筆をおこなっていたのは自由がひとつの言葉以上である国だったということだ。民主主義、平等、友愛、絶えず彼が語っていたそれらは遠い理想ではなく、彼の目の前に存在した何事かだった。十九世紀半ばのアメリカ人は自分たちが自由で平等であると感じていて、実際、純粋な共産主義社会の外側で可能な範囲においては自由で平等だったのだ。貧困はあったし階級区別さえあったが、黒人を除けば恒久的な極貧階級は存在しなかった。皆がその内に何か核のようなもの、知識を持ち、それでまずまず生きていくだけの稼ぎを得ることができた。それも誰かにへつらうこと無くだ。マーク・トゥエインの描くミシシッピのいかだ乗りや水先案内人、ブレット・ハートの描く西部の金鉱掘りの様子を読むと、彼らは石器時代の人食い人種とはかなり違って見える。その理由はたんに彼らが自由な人間であるためなのだ。しかしこれは東部の州の平和で家庭的なアメリカ、若草物語やヘレンの赤ちゃん、バンゴーからの汽車の旅で描かれるアメリカであっても同じことだ。生活は快活、気ままで、それらの作品を読めばまるで腹の中に感じる肉体的感覚のようにそれを感じられる。実のところその手腕は極めて稚拙だが、ホイットマンを称えるとすればそれは何を感じるかではなく、何を感じるべきか教えてくれる作家のひとりであるためなのだ。アメリカでの生活の荒廃を目にする前に彼が死んだことは彼の信念にとってはおそらく幸運なことだっただろう。それは大規模産業の隆盛と安価な移民労働者に対する搾取とともに訪れたのだった。
ミラーのものの考え方はホイットマンのそれととても良く似ていて、彼の作品を読んだ者はほとんど全員がそれを指摘する。北回帰線はとりわけホイットマン的な文章で終わる。その文章ではわいせつな行為、詐欺、けんか、酒宴、愚行の後、物事のありのままに対するある種の神秘的な受容の中で彼は座り込んでセーヌ川が流れ去っていくのを見つめる。だがしかし彼が受け入れているものは何なのだろうか? まず第一に、それはアメリカではなく古来ヨーロッパの積み重なる遺骸である。そこでは土の一粒に至るまでが無数の人間の体を経てきているのだ。第二に、それは拡大と自由の時代ではなく恐怖、独裁、統制の時代である。現代のような時代を「受け入れる」と言えば、それは強制収容所、ゴム警棒を受け入れると言うことに等しい。ヒトラー、スターリン、爆弾、飛行機、缶詰食料、機関銃、暴動、粛清、スローガン、ベルトコンベヤー、ガスマスク、潜水艦、スパイ、工作員、報道検閲、秘密刑務所、アスピリン、ハリウッド映画、政治的殺人。もちろんこれらにとどまらない。これらは中でもとりわけ目立つものに過ぎない。そして全体的に言えば、それこそがヘンリー・ミラーの態度なのだ。常にというわけではない。ときおり彼はごく普通の文学的ノスタルジーのようなものの兆しを見せるからだ。黒い春の初めの方、中世を賛美する個所には長い一文があり、それが散文としては近年書かれた中で最も優れたもののひとつであることは間違いない。しかしそこに見られる態度はチェスタートンのそれとたいして変わらない。マックスと白食細胞には産業主義を嫌う文学者によくある視点からの、現代アメリカ文明(朝食のシリアル、セロファンなど)に対する非難が書かれた個所がある。しかし、おおまかに言えばその態度は「それを丸呑みにしようじゃないか」というものだ。そしてわいせつさ、生活の汚れたハンカチ的側面に対する表層的な没入はそれゆえなのだ。それは表層的なものに過ぎない。実のところ、ありきたりな日常生活はフィクション作家が普通それと認めるよりもはるかに多くの恐ろしいものから成り立っている。ホイットマン自身は彼の同時代人が口にするのもはばかられる経験をしていることをおおいに「受け入れて」いた。彼は大草原を描くだけでなく、都市をさまよい、自殺で砕けた頭蓋骨や「自慰者の灰色の病的な顔」などについて書き留めた。しかし、少なくとも西ヨーロッパにおいては、疑いなく現代はホイットマンが著作をおこなっていた時代よりも不健康で希望の少ないものである。ホイットマンと異なり、私たちは縮んでいく世界に暮らしている。「民主主義の展望」は有刺鉄線によって終わった。創造と成長の感覚は減退し、際限なく揺れ続けるゆりかごはますます遠くなり、際限なく吹きこぼれるティーポットがますます近づいている。文明をありのままに受け入れることは腐敗を受け入れることを意味する。それは力強い態度をとることを止め、受け身の態度に……その言葉が何らかの意味を持つとして「退廃的」にさえ……変わることなのだ。
しかしある意味で経験に対して受け身であったからこそ、ミラーはもっと目的意識に富んだ作家よりも普通の人間に近づくことができたのだ。なぜなら普通の人間もまた受け身なものだからだ。狭い内輪(家庭生活、そしておそらくは労働組合や地域政治)の中では自身の運命の主人であると感じるが、大きな出来事に対しては自然の力に対するのと同じくらい無力である。未来に影響を与えようと努力するにはほど遠く、ただ横たわってなすがままにされるのだ。過去十年の間、文学はますます深く政治に関わってゆき、その結果、今や過去二世紀の間のどの時期と比較しても普通の人間のための居場所は少なくなっている。広がっている文学的態度の変化はスペイン内戦について書かれた作品と一九一四年から一九一八年の間の戦争について書かれた作品を比較すれば見て取ることができる。少なくとも英語で書かれたものについて言えばスペイン戦争の作品でただちに目を引くのはその衝撃的なまでの鈍さと劣悪さだ。しかしもっと重要なのは右派、左派を問わず、そのほとんどが政治的な視点から何を考えるべきか教え諭す自信過剰な党支持者たちによって書かれているということなのだ。一方で世界大戦についての作品はその全体像がどのようなものか理解するふりすらしない兵卒や下級将校によって書かれていた。西部戦線異状なし西部戦線異状なし:ドイツの作家エーリヒ・マリア・レマルクによる小説や砲火砲火:フランスの作家アンリ・バルビュスによる小説、武器よさらば武器よさらば:アメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイによる小説、英雄の死英雄の死:イギリスの作家リチャード・アルディントンによる小説、さらば古きものよさらば古きものよ:イギリスの作家ロバート・グレーヴスによる小説、歩兵隊将校の思い出歩兵隊将校の思い出:イギリスの作家ジークフリード・サスーンによる小説、ソンムの準大尉ソンムの準大尉:イギリスの作家マックス・プローマンによる小説。マーク7世名義で発表された。といった作品はプロパガンダ宣伝者ではなく、犠牲となった者によって書かれていた。実際のところ彼らが語っているのは「いったいこの騒ぎは何だったのか? それは神のみぞ知る。私たちにできるのはただ耐えることだけだった」ということなのだ。そして彼らが戦争についても、全体的には悲惨さについても書いていないのに、これは現在の流行りである全知的なそれよりもミラーの態度に近いものなのだ。彼がパート編集者だった短命に終わった定期誌であるブースター誌は宣伝の際に自身のことを「非政治的、非教育的、非進歩的、非共同的、非道徳的、非文学的、非一貫的、非現代的」と表現していたがミラー自身の作品もそれとほとんど同じ言葉で表現できる。それは群衆からの、下層からの、三等客車からの、ごく普通の非政治的・非道徳的な受け身の人間からの声なのだ。
私は「普通の人間」という言葉を非常に漫然と使ってきたし、当然のようにこの「普通の人間」が存在すると考えてきた。これは現在、一部の人々には否定されているものだ。私はミラーが描いている人々が大多数を構成する人々であると言うつもりも、ましてや彼が描いているのがプロレタリアートであると言うつもりもない。イギリスやアメリカの小説家でいまだに真剣にそうしたことを試みている者はひとりとしていない。そしてまた北回帰線に登場する人々は普通と呼ぶには少々不十分である。彼らは無為に時間を過ごし、いかがわしく、多かれ少なかれ「芸術的」なのだ。すでに述べたとおり、これは残念なことではあるが国外に住むことの避けられない結果である。ミラーの「普通の人間」は肉体労働者でも郊外の屋敷持ちでもなく、路上生活者、没落者、山師、金も無い根無し草のアメリカ出身の知識人なのだ。それでもなお、こうした人々の経験はもっと標準的な人々のそれと重なる部分が多い。ミラーは自身の非常に限られた取材源を最大限に生かすことができた。それは彼が自身をそれらに重ね合わせる勇敢さを持ち合わせていたためだ。普通の人間、「平均的で猥雑な人間」に対してバラムのロババラムのロバ:旧約聖書「民数記」22章からの引用のように声を上げる力が与えられたのだ。
これは時代遅れ、あるいは少なくとも流行遅れであるように思われることだろう。こうした平均的で猥雑な人間は流行遅れだ。セックスへの没頭や内的生活への誠実さは流行遅れだ。アメリカ出身のパリ市民は流行遅れだ。現在のような時期に出版された北回帰線のような作品が退屈な気取り趣味か、何か普通でないもののどちらかであることは間違いない。そしてこの作品を読んだ人々の大多数はこれが一流のものではないことに頷くだろうと思う。その正体を明らかにしようとすることには価値がある。この作品は現在流行している文学的手法に捕らわれていないのだ。しかしそうした時に気がつくのは、この作品がその背景……つまり世界大戦からの二十年の間の英語文学の全体的発達と対立しているということなのだ。